更新記事一覧
(28/01/2014)
1.認知症について
(その1)
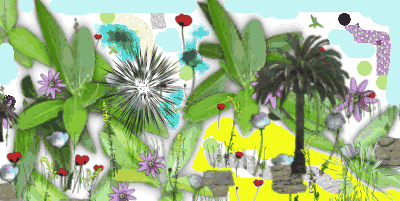
(記事は更新されてない場合が多いので、ご面倒ですがWebページ検索欄周辺の⟳マーク(更新あるいは再読み込みボタン)をクリックしてください。また、Safari以外のブラウザは、文字が読みにくい場合があります。右上上部の「リーダー」の青枠をクリックすると読みやすくなります。)
Instagram にて、直近の状況を画像で掲載中です。
よろしければ、下記のリンク先等もしばしば更新していますので、訪れていただければ幸いです。写真もあります。
| やまぼうしブログ | タラから南インド へ | Life of Tara | My Photos | Kun Esperantistoj | FaceBook(Kunio.Ooki) |
| (11/07/2019) | (20/04/2020) | (11/11/2018) | (14/03/2014) |
また、Livedoor.Blogで修復奮闘の画像を掲載中
人間の未来に対する3人の提言(IOM Proposal) を掲載しました。
IOM Proposal の注釈に、「人々への奉仕」を加えました。(02/01/2018)
2018年8月1日にIOM Proposalを IOMR Proposal(人間の未来に対する4人の提言)と変更しました。変更後のアイアーさんのコメントは
IOM ProposalのIOMR Proposalへの進化について(28/08/2018) に掲載されています。
「時間について」は、別ページで連載中です。(28/01/2014)
2019年8月に古代インドの長いお話(1〜4)を青少年たちへのマハーバーラタの解説として掲載しました。
2023年11月9日にCD解説としての音楽の贈り物を掲載しました。
2023年11月10日に書くことと発表すること(個人的な歴史)を掲載しました。
更新記事一覧
(28/01/2014)
1.認知症について
(その1)
このホームページを立ち上げて、一ヶ月が過ぎました。今年は年の始めから母の病死や地震などが続き、予定していた三度目のインド旅行をとりやめて、このホームページの作成に専念したのでした。しかし作成したからといって、それだけで誰でも見てくれるわけではありません。残り少ない人生ですが、同じような考えを抱いている方々との交流を目指して、まだまだ努力しなければならないと思っています。
ところで、同居している私の父は88歳になりますが、ここ数年認知症の症状がひどくなってきています。この夏の暑さで体も弱ってきていますが、窓を開けたまま冷房をしたり、風呂の水を出しっぱなしにしたり、一人で放っておくことはできなくなりました。
病院での検査ではそんなに重症ではない認知症だが、CTスキャンでは、かなり脳の中が萎縮しているということでした。
しかし私がここで言いたいことは、脳の科学的な分析と認知症の関係ではありません。認知症の症状の一番の特徴である、直近の出来事の記憶がなくなってくるという事実に注目したいのです。父はもう数分後には自分のやったことを覚えていません。病院へ行く支度をしても、すぐに今日はどこに行くのかと聞いてきます。彼の日常の行動は、遠い過去の記憶と今までの習慣に頼っています。新しいことを覚えて新たな習慣にすることには、途方もない努力を要します。本人も数分前のことを思い出せないことに、悲しい表情を見せることがあります。私がちょっと留守をして帰ってくると、どこかからの頂き物がテーブルに置いてあるのです。誰からもらったのか聞いてみても、忘れたと言います。すると横にメモ書きの紙切れが置いてあります。そこにかろうじて父の字で名前が書いてありました。ああ、あのおばあさんが持ってきたのだね、と父に確認しても分からないと言います。それでも父は、忘れるといけないと必死でメモったのでしょう。父の書いた名前の方に電話をすると、その通りでした。父の必死の配慮が感じられて、うれしくも悲しい気持ちに襲われました。
こうして、直近の記憶が次から次へと失われていくということは、一人の人間にとってどういうことを意味するのでしょうか。人間としての喜びも悲しみも現れては消え去っていくのみです。過去であるが故の悲喜こもごもとした味わいは何もありません。そこで私は二つの意味を考えてみました。
一つは、人間というものは、老いて死に近づくと、誰でも同じような状況になるのではないかということです。人間という動物的な意識から、植物的な意識へ、そして土に戻るという鉱物的な意識へと、変化していくのではないか。ですからヴェーダの説く四住期の最後の遊行期もこのような老化の過程とオーバーラップするのかもしれません。認知症は我々人間が誰でも経験する事態の先取りなのかもしれません。
それともう一つ考えたことは、こうした先取りの人間たちは、古来から存在していたのですが、昔は家族や地域社会が、彼らの存在を認め、それなりに彼らを見守ってきたということです。今はもう家族がいても、テレビとにらめっこの個室に追いやられるか、老人ホームに預けられてしまいます。誰でもたどる道筋を、先取りするだけで病気として隔離されてしまう状況が蔓延しています。精神科の病棟や介護サービス施設はどこも満杯です。それはもう日本では押しも押されぬ巨大産業に成長しています。私はこれからもこの問題を考えていきたいと思います。
(2011年7月19日)
2009年7月に二回目のインド旅行で、私は再びカーンチ・ムートを訪れました。ここでは偉大な第68代マハーチャリアを引き継いだ二人のアーチャリアが教えを説いています。70を過ぎた第69代アーチャリア(ホーリネス.シニア)とまだ40代の第70代アーチャリア(ホーリネス・ジュニア)です。前回の訪問で、私はホーリネス・シニアとは面会できたのですが、そのとき不在であったジュニアの方に、今回は是非会いたいと思っていました。
大勢が並んでいる公の拝謁場所に行くとホーリネス・ジュニアがニコニコと私を呼び入れました。私は彼にお布施と、たらの芽庵便りの英訳と英和辞典を渡しました。英和辞典は前回ここで知り合った私のグル、アイアーさんがメールでホーリネス・ジュニアは語学に興味があるので日本の辞書を贈り物にするようにとのアドバイスがあったためです。しかしここで落ち合うはずだったアイアーさんは奥さんが病気で入院したため来れず、代わりに彼の友人のメータさんが、ジュニアとの会見の世話をしてくれました。
こうして私はホーリネス・ジュニアーと会見することができました。私はホーリネス・ジュニアに大野博士のタミル語と日本語の類似点を、表を示しながら説明すると、周囲の従者からオーッつと声が上がります。ジュニアもうなずいています。当時世界中で皆既日食が見られる状況でしたので、彼からは日本では皆既日食の時、何か宗教的な行事をするのかと聞かれました。日本では太陽に関する宗教的な行事は古代ではあっただろうが、今は科学的な興味や珍しさから話題になっているだけだと答えると、彼はがっかりした様子でした。
数日後、私はメータさんにお願いして二度目の会見に臨みました。今回は一般の会見場所ではなく、特別な奥の部屋に招き入れられました。
再び日本語とタミル語のこと、そして天皇のことについて聞かれました。日本の天皇は国の象徴であって政治には関与していないと答えるとホーリネス・ジュニアは納得したようでした。そしてやおら天井を見上げてシンボル!と叫びました。ピータの教えでは政治は社会をまとめるために必要ではあるが、政治手法や政策はどうしても妥協の産物であり、不純なものである。政治に倫理や教育を任せるわけには行かない。宗教こそ倫理や教育の基礎であり、政治と宗教は切り離すべきである、と。
ところで私が床に正座しているのを見て、年老いた従者の一人が足を崩して胡坐でもかまわない、とタミル語で盛んにしゃべります。最初は何を言っているか分かりませんでしたが、ようやく身振りでわかりました。足を崩すとみんながどっと笑う。和やかな雰囲気に、ホーリネス・ジュニアと一緒に記念に写真を撮りたいと申し出ると、従者がカメラのシャッターを押してくれました。
帰国後、この会見の結果と写真をアイヤーさんにメールで送ると、すぐに返事をもらいました。その一部をご紹介します。
「私は、あなたがカーンチ・ムートで撮った写真を見ました。あなたの右に座っているのがメータですが、彼は銀行を退職して、家族とカーンチに住んでいます。彼の後ろに立っているのはチャリさんです。彼は毎日ムートで行われる神に捧げる歌のプログラムを作成しています。あなたの後ろにいるのがまさしく顔を輝かせて満身の笑みを浮かべているホーリネス・ジュニアです。すばらしい写真です。私は歓喜と力をこの写真から得ました。そして周りの人にもこの写真を見せてあなたを彼らに紹介しました。
ホーリネス・ジュニアは、リグヴェーダを他の人が7年かかるところを3年で習得しました。両親と一緒にチェンナイに住んでいる彼の弟もそうでした。彼らの父親はヴェーダの先生でしたから、子供たちに教えることができました。
ホーリネス・ジュニア(正式の名前は、シュリ・シャンカラ・ヴィジャエンドラ・サラスワティ)は1983 年、前任者と同様に彼が13歳のときに、この修道施設に入りました。
二人のアーチャリア(ホーリネス・シニアとホーリネス・ジュニア)は現在、他の人々に役立つような生活をするように、人々を導いていく仕事に従事しています。彼らが行うカマコチ・ピータでの日々の礼拝でさえも、人類全体の幸せをも祈るものなのです。彼らを含むこのピータにおける、代々のアーチャリアは、古来からの伝統に従って、皆同じ仕事に従事してきました。すなわち、大切な宗教儀礼としてのプージャを執り行い、彼らを訪れる人々を祝福し、援助するという日々の行為を、今まで延々と引き継ぎ、続けてきたのです。」
このように、南インドの宗教施設では、地元の人々と密着した祈りと儀式と教示が、遠い昔から同じように毎日繰り広げられているのです。
(2011年8月11日)
認知症についてまた少し書いてみます。巷では、新薬が開発されたと騒いでいます。しかし一度認知症にかかると、薬ではなかなか直せないと思います。というのも前回書いたように、認知症は人間にとって構造的で、至るべくして至る症状だからです。父が現在飲んでいるアリセプトにしても、進行を抑えるとは言いますが、気休めに過ぎないと思っています。至るべくして至るとは、ぼけや老衰や、物忘れは誰でも年取ると経験するように、徐々に進行していくものだということです。確かに徘徊や特定のものへの偏執的なこだわりが顕著になることもありますが、基本は現実の世界に興味が薄れてきて、過去の良い時代にのみ依拠して、淡々と来るべき死を待つといった状態だと思います。
父の場合は放っておくとほとんど椅子に座ってテレビを見たまま眠っています。それでも趣味である畑仕事のことは完全に忘れることはなく、畑に出て草むしりなどを夢中でやることもあります。週二回は一日中デイサービスに通っています。介護する我々家族もほっとするひとときですが、89歳になる父にとっては体力も使うので週二回が限度です。ですからそれ以外の日はできるだけ規則正しい生活をしてもらうために、週間予定表を作ってテーブルの上に置いておきます。具体的な日程として、朝晩の血圧測定、夕方の犬の散歩、庭の水やり、簡単な部屋の掃除などは必ずやってもらうようにしています。
もちろんそれらとて忘れることも多いし、水やりで泥を飛ばし、車を泥だらけにしたりします。そんな時、私は本気で父を怒ります。よくテレビなどで、認知症の患者を怒ってはいけない、と言いますが、それは実際に身内に患者がいない人の考えのような気もします。怒らざるを得ないことは毎日の介護で山ほどあります。怒っても良いのです。昔は怒られると、本人は近所の人に怒った家族の愚痴を漏らして、慰められていたのでしょう。そういう近所付き合いの機会は少なくなったにしても、怒られるという嫌な思いが、また我々とのつながりを保っているのです。
怒った後には時折優しくしたり、喜ばしたりすればいいのです。おじいちゃん、今日は一日怒られなくてよかったね、というと、ああ、そうかい、と言葉が返ってきます。そんなこんなで、みんな死に近づいていくのです。ただただ長さが違うというだけで。
(2011年9月4日)
私は、疲労のため、この数日、特別なことは何もしませんでした。私には残り少ない人生で、少しでも意味のある仕事をしたいという気持ちはあるのですが、
時折思うように体を動かすことができません、そして、私はまる一日、日常的な活動以外はほとんど何もできずに休むばかりです。
もちろん、私は時々、一日中活発にいろいろなことをすることができます。しかし、その後、私は相変わらず深い疲労に陥ります。人間にとって疲労とは、何でしょうか?
私は、カフカの小説、城を思い出します。小説では、城の官僚が、疲労が人間へのすばらしい贈り物であることを語る場面があります。我々には疲労、つまり我々の体に一定の制限があるというだけで、我々は効率的に生きることができる。それが人間の世界というものだ。彼はそう言います。我々は時折避けられない疲労を持つからこそ、限られた期間であっても、意味のある人生を送ることができる。そう思わなければならないのかもしれません。
(2011年10月2日)
我々はEUの財政危機についてどのように考えるべきでしょうか。国というものの存在のあり方が問われているのかもしれません。国とは、何でしょうか。ネイションはどちらかと言えば、ある民族的な集団を意味するのでしょう。他方でステイツは現代の資本主義社会が最終的に到達したコミュニティを意味します。我々にとって国としてどちらが良いのでしょうか。両方とも歴史の必然性な結果ですから、どちらがよいかについて結論づけることはできません。しかし、最近のEUの財政危機は、人間のための将来のより良い共同体組織とは何であるかについて、我々に考えさせてくれます。
私は、資本主義の諸国家がこれまで我々に提供してきたすべての物事が悪いとは思いません。しかし、現在、資本主義の諸国家は、ある種の袋小路にさしかかったように思えます。アメリカのようなほとんどの先進諸国は、深刻な失業状態に陥り、社会的な不安を増大してきました。他方、中国、インドとブラジルのような発展途上の国家は、彼らの急成長で富める者と貧しい者間のギャップを増やしてきています。そのような発展途上の国家は、海外進出とインフレーション方策を増大することによって、先進諸国と同じような矛盾を展開しようとしています。我々は、こうした諸国家に我々の将来を託すことができるのでしょうか。私は、この質問が明らかにEUの将来の問題に当てはまるのではないかと思うのです。
EUは、将来国という枠組みを乗り越えることができるでしょうか。それともEUというものは、国と経済ブロック・コミュニティの間の妥協の産物に過ぎないのでしょうか。EUが本当に将来の人間コミュニティを目指すつもりならば、段階的な方策として、今何をしなければならないのでしょうか。EUの指導部は、当面はギリシャを経済危機から救わなければならないでしょう。そのためには、彼らはEU内の民衆に根気よく、彼らの本当の理念を民衆に認めてもらうよう説得しなければならないと思います。彼ら指導部は、EUの民衆は、現在の諸国家間の枠組みの向こうにある新しい社会を造るために、これからも長い困難な道に耐えなければならないということを根気よく説明しなければならないでしょう。
(2011年11月3日)
ナマステ (Namaste) はヒンドゥー語の挨拶の言葉として、インドを訪れた人は誰でも出会う言葉です。両手をあわせて、相手を優しく見つめて、この言葉を発するのがヒンドゥー教の本来の挨拶です。この言葉の由来は、元々はサンスクリットです。その本来の意味について、私の友人アイヤーさんがメールで何度も説明してくれたので、その深い意味をここで紹介したいと思います。
「ナマステ。我々はすべての手紙をこの言葉で始めます。ナマは、私はお辞儀をします。テは、あなたに対して、という意味です。この言葉を我々は眼前にいる人への挨拶や手紙での挨拶に使用します。」
「ナマステ。そうあなたに言うことによって、私はあなたの心の中に住む全能者を敬っているのです。あなたの前にひれ伏す、という意味でもあるナマステを、手を合わせながら言うことで、あなたの心の中の全能者を敬う行為、それが挨拶するということなのです。」
「ナ、は否定を表します。マ、は私のものを、テ、はあなたのものを意味します。したがってナマステは、私の持っているものは私のものではなく、あなたのものである。あなたは創造者であり、私の周りのすべてのものを創造しました、ということを意味します。この言葉を発しながら、我々は両手の平をあわせて、お互いが向かいあって、祈りと謙虚な気持ちを込めて挨拶するのです。」
「ナマ、という言葉は、あるマントラの言葉です。マントラはヴェーダに記された聖なる言葉で、サンスクリット語で記されています。ここでのマントラはアンクラ・マントラと言います。アンクラとは芽を出すことを意味します。両手を閉じた手のひらのことをアンクラ・ムードラと言います。ムードラは身振り手振りという意味です。植物が種子から芽を出して成長するように、我々人間の心の成長は謙虚な気持ちと目の前の相手の心の中に住む全能者に対する祈りから生まれてくるのです。それがナマステという挨拶の意味です。このような、他人に対する謙譲と祈りの態度は、膝を折り曲げて、頭を深く下げる日本人の挨拶にもみられます。このように広く東アジアの諸国にみられる習慣は、謙虚さを重視し、他人の中に神聖さをみるこれらの諸国の古来からの文化を暗示するものです。しかしながら、時の経過と外部社会との混淆により、これらの気高い理念は希薄になり、意味のないものになり、そして世代を経るとともに、ついには消え失せてしまうのです。」
「親愛なる大木さん、あなたがナマステの起源をメソポタミア文明にまでさかのぼるのではないかと言いましたが、私の知る限り関係はないようです。これはサンスクリット語で、ナマとテに分解できます。テはあなたを意味し、ナマは平伏することを意味します。したがってナマステの全体の意味は、私はあなたの前にひれ伏しますということになります。文字通りの意味は、ナマは私ではない、あるいは私のものではないという意味です。ナは否定の意味です。他者に挨拶をしながらナマステと発するように、我々は礼拝においてもナマステという言葉を使用します。その隠された本当の意味は、私はあなたの中に存在する神聖なものを敬いますということになります。」
こうしてアイヤーさんは私に手紙をくれるたびにナマステの意味を説明してくれました。最後の引用は、私がナマステの本来の意味と単語はメソポタミア文明にまでさかのぼるのではないかと質問したことに対する回答です。ナマステの精神、他者を敬うこと、そしてそこから導かれる、他者への思いやりは、古代文明に共通する、さらには人類一般に共通するものではないかと思われたからです。アイヤーさんの答えは日本人の挨拶の精神にも言及しており、彼も人類共通の普遍性としてナマステの精神を考えることを否定してはいないのです。
アイヤーさんは1968年頃インドと日本の文化交流で日本に三ヶ月ほど滞在しています。したがって日本人の挨拶の意味、日本人の他者への思いやりをよく知っています。ホームステイした家庭の主婦が、菜食主義者である彼のために一生懸命おいしい料理を作ってくれたのを忘れないと書いていました。
他者への思いやりは古来から日本人の心の中にあります。そしてそれは古来からの人類共通の普遍性でもあります。そのような他者への思いやりをヴェーダでも説いているのです。その象徴的な言葉がナマステなのです。
ガンジーもそのことに関して自伝の最後に述べています。
「人は、自由意志から、自分を同胞の最後の列に置くようにしない限り、救いはない。非殺生は、謙譲の極限である。」(中公文庫、蝋山芳郎訳)と。
これはインドの大地から発せられた言葉、しかし古来からの普遍的な人類の言葉でもあります。
(2012年1月25日)
アルジュナは古代インドのとてつもなく長大な物語、マハーバーラタに登場する主人公的な人格のひとりです。血縁が同じであるものが入り交じったパーンダヴァ族とクル族が対立し、果てしなく戦いを演じていきます。そして最終決着をはかるべく、パーンダヴァ族の5王子とクル族100人の王子がそれぞれ総勢を引き連れてクルの大平原に対峙するのです。5王子の一人でパーンダヴァ族側の総帥が文武両道に秀で、一族からも崇拝されているアルジュナです。両族の壮大な布陣は、日本でいえば天下分け目の戦いとして、関ヶ原の場面を思わせるようなスケールで、戦いの前の緊張がいやが上にも高められていきます。アルジュナはこのような身震いするような場面で敵方と対峙するのです。しかし、ここでアルジュナは敵方に親しんだ友や師と呼ぶべき親類縁者がいることから、このような戦いのむなしさを思い、憂いに沈みます。そこで彼の友であり従兄弟でもあり、彼のそばに従うクリシュナが、武人として躊躇せず戦うよう彼を説得します。この説得の場面が有名なバガヴァッドギータ(Bhagavad-Gita)という、ヒンドゥー教の重要な教えの一節なのです。
クリシュナはアルジュナに対して、次のように言います。
「私利私欲を離れ、執着なく、結果の成否を度外視して、なすべき行為をなせ。
肉体のうちなる霊魂はうたれず、不死不滅である。常住にして不滅、無量無辺なる霊魂に対し、これなる肉体は、限りあるといわれる。されば戦うが良し、バラタの御子よ。万物の体内に座すこの霊魂は、永久に損なわるることなし。されば、バラタの御子よ、すべて生きとし生けるものを、そなた嘆くべからず。定めたる行為をば、そなたはなせ。行為は無為に勝る。そなた無為なるに、身体の維持すらも叶わざるべし。我もし行為をなさざれば、この世は壊滅せん。我にとり、またそなたにも、アルジュナよ、あまたの過ぎにし生死あり、その一切を我は知る。そなたは知らず、剛勇手ききのつわものよ。」
(講談社 学術文庫 鎧淳訳)
クリシュナはヴィシュヌ神の化身として、古来ヒンズー教徒の間では絶大な人気を誇る英雄です。アルジュナと同様に美貌で多くの女性を引きつける存在でもあります。その彼がアルジュナに、敵方が友や恩師あるいは親族であったにしても、ここで戦うことがあなたのなすべきことなのだと説得するのです。
そうは言っても、アルジュナの躊躇も理解できます。自らの部族のために友や恩師と戦うことは許されるのか。友や恩師どころか、この戦いで多くの戦士が命を落とすことだろう。このような殺戮はむなしい。私はこのままこの場を去ってしまいたい。それがアルジュナの素直な気持ちでしょう。もし、ここでクリシュナではなく仏陀がいたとしたら何と言ったでしょうか。もちろんクリシュナのように戦えとは言わなかったことでしょう。では、武器を捨て、彼に従う多勢の兵士を残して、一人戦場を去れ、とアルジュナに勧めたでしょうか。もちろん仏陀はここまでアルジュナに付き従うことはなかったでしょうが、万が一ここにいてアルジュナにどうしたら良いかと問われたら、無言で仏陀自らがその場を去ったことでしょう。ここのところが仏教とヒンズー教の大きな分かれ目ではないか、またヴェーダ学者のシャンカラがヴァガヴァッド・ギータの解釈に最も思い悩んだところではないかと思うのです。
ではヒンズー教の最も重要な神の一人であるクリシュナがアルジュナに語った真意は何なのか。私は次の三つの意味を考えます。
一つは最も一般的な意味です。即ち部族の命運をかけて、ここまで多勢の兵士を引き連れてきたのだから、どうして引き下がることができよう。時は刻々と前進して戦う方向で刻まれている。武士として雄々しく戦い、新たな歴史を刻め、と鼓舞することです。二つ目の意味は、肉体は滅びても魂は滅びないということです。汝の友を殺戮しても、友の魂までは殺戮できない。友の肉体は滅びるべくして滅びる。であるから限りある肉体を、今ここで葬るしかない。それが今、ここで汝に与えられた使命なのだと。そして三つ目の意味は、汝が今、ここで敵に立ち向かい敵を殲滅する行為は、汝のみに与えられた、当然なさなければならない行為だということです。クリシュナはアルジュナにそうした行為をなさなければ、世界が消滅するとまで言っています。つまりここで戦うのは汝に与えられたカルマなのだから、それを実行するしかないという考え方です。カルマはそれを担う者の業とか宿命と訳されますが、ここではまさしく敵陣になだれうって戦うことが、アルジュナの魂の行き着くべきところ、それで世界が動いていく、なくてはならぬ行為なのだと言っているのです。
一つ目の意味は誰でもそれなりに理解できます。しかし二つ目、三つ目の意味は、果たしてヴェーダの教えに背くことはないのでしょうか。ヴェーダではむしろ行為を放棄し、執着を断って、一人遊行の道へと進むのが理想とされているからです。ここで古代のヴェーダ学者シャンカラは、苦渋の解釈をします。つまり人それぞれのカルマを導く教え(ダルマ)には二種類ある。一つは行為をうながすダルマであり、もう一つは行為を抑制するダルマである、と。そして行為を促すダルマでは、行為に身を任すことは、決して行為の結果に執着することではなく、行為をなさざるを得ない使命感の中に、自己への執着をも断念することだと教えるのです。だから本来のダルマである行為を抑制する知のダルマと矛盾するものではない。行為の中で自己を無に帰せしめることによって、行為の完全なる放棄であるアートマンの知へと登り詰めていくことができると。しかしそれもなんだか苦しい解釈で、本当にアルジュナを納得させることができたかどうかは疑問です。
一般的にヴァガバッド・ギータの言わんとするところとして紹介されるのは、引用の冒頭の部分にもあるように、行為の結果に執着することなく、私利私欲を排して、自己のなすべき義務を果たせということなのでしょう。しかしギータには次のような言葉もあります。
「苦楽、得失、勝敗を等しとして、かくて合戦に参ずるが良し。かくしてそなた、罪過を得ることなからん。」
苦楽、得失、勝敗を等しとするとは、それらに執着するなということでもありますが、罪過を得ることもないという言い方はどうしても仏教にはない言い回しです。マハーバーラタの壮大な物語の中の戦いは、円盤のようなものを投げて相手を切り刻んだとしても、相手はすぐに回復し、なかなか死なないといった場面が至る所で展開されます。つまりそこでは永遠に死なない魂と簡単に死滅する肉体との混淆、そして神と人間の戦いの混淆が見受けられます。そこでは魂も肉体も、神も人間も、善悪も苦楽も、混淆する中で、それらにとらわれない境地が行為のカルマとして浮かび上がってくるのです。こうした表現や境地は初期仏教にはないものであり、やがてタントリズムや密教に取り入れられて発展してくるのではないかと思われます。
戦う前のアルジュナの苦悩は生身の人間として当然のことです。また彼は行為のカルマやヨーガの教えにそのまま従う必要もないのです。そんなことを知らなくともここまできたら、悶えながらも戦うしかないのです。しかしそこに理屈を付けて壮大な物語の一部にするところがヒンズーの教えの面白いところです。そこから仏教の正統派が道徳的に純化していくと同時に、一方でタントリズムや密教、チベット仏教なども生まれてくるのです。それがヴェーダの教えに端を発したヒンズーの多様性と奥深さだともいえます。
(2012年2月23日)
沖縄の米軍基地移設問題がメディアを賑わしているようですが、本当のところ究極的にはどうしたら良いのか、政治家やマスコミには、解決すべき方向が見えているのでしょうか。沖縄の人々の長年の苦しみを除去しなければならないということでは、表面的には皆が一致しているのでしょう。しかしながら同時に日本の安全を保障するためには、日米同盟がどうしても必要であり、アメリカの極東戦略を無視するわけにはいかない。そのためには沖縄は、相変わらず軍事的にも重要な拠点である。したがって沖縄の住民の負担を極力軽減する形で、米軍基地の沖縄での問題を解決していかなければならない。これが大方の政治家やマスコミの意見なのかもしれません。しかしそうは、あからさまには言えないのが政治家であり、またマスコミは、沖縄県民や沖縄の行政庁の断固反対の様子を映像として流しはしますが、アメリカと地元住民の間に挟まれて後手に回るだけの日本政府の空回りを映し出すだけに終わっています。
どうしてこうなってしまったのか。それはやはり日本の防衛問題を制約する憲法第9条の存在が大きく関わってくると思います。9条は次のように表現されています。
「1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
この文面だけを見ると、あまりにも理想的すぎて、国民のために国を守るという点では、国としての責任を放棄しているようにも思えます。政府は「専守防衛」論による自衛隊の強化や日米安全保障条約に基づく米軍の援助を期待していますが、どちらもいざとなった時に、本当に国民や国民の財産を守れるのかは疑問です。というのも国家間の政治力学の基礎には相応の軍事力が対応しており、また国家間の武力紛争はいつの時代にも、どこかで起こっているのが現実だからです。
例えばロシアが領土問題や漁業問題のために北方領土から広い範囲にわたって軍事的にロシアの権益を強化してきた場合、あるいは中国が東シナ海の海底資源をさらに自国のものとするために軍事力を日本の海域に増強してきた場合、日本は自国の権益をアメリカや国連に訴えかけることなどの外交努力で守ることはできるのでしょうか。誰もそれが可能だとは思っていません。それでも、この資本主義経済の繁栄と民主主義の謳歌のもとで、当面はそういうことは起こらないだろうと思っているに過ぎません。日本政府は憲法第9条があるが故の、自衛隊の専守防衛と日米同盟への依存で、こうした問題を曖昧なままにしてきました。その曖昧さの象徴が現在の沖縄の米軍基地問題だと思います。
では、憲法第9条はそのような曖昧さの法的根拠を提供し続けているに過ぎないのでしょうか。アメリカの核の傘のもとに、経済発展に明け暮れた日本の平和ボケはもうこれくらいにして、日本国民は本気で自国を守るために憲法を改正して、専守防衛などという非現実的な軍備ではなく、真に国民を守るための国防体制を構築すべきだという考えもあります。現在の資本主義経済の核となる国家というものが、人類にとってこれからも永遠に存続するのなら、それも一つの選択肢だと言っていいのかもしれません。いつまでもアメリカの防衛力に頼るということは、どう考えても戦後の遺物であり、日本が今まで一国の主権国家として外交的に主体的、積極的な対応がとれなかった所以でもあります。
憲法9条は我々が教科書で学んだように、崇高な理想ではあります。しかし現実には、日本は戦後の妥協の産物として、アメリカの核の傘のもとに入り、そのことによって、資本主義国家群の中で国としての権益をなんとか維持してきたに過ぎません。日本の憲法9条が世界の平和的な理念の象徴として、国連などを通じて位置づけられてきたわけではさらさらありません。他の国には、ドイツと同じような日本の独裁的な軍事国家がもたらした悲劇の再発を防止するためにある法律だな、としか思われていないことでしょう。憲法第9条に関する本質的な議論は、アメリカの核の傘にあって、経済発展を謳歌してきた日本人にとって、積極的に展開されることなく、今日に至ったように思えます。沖縄の米軍基地問題が政府主導で解決していくことができないのも、この9条の問題の国民的合意の曖昧さにあります。
では憲法第9条は改正すべきなのでしょうか。資本主義国家間のゲームがこれからも永遠に続いて行くとするのなら、今の日本の防衛能力は極めて中途半端な状況であることは事実です。
しかしどうでしょうか。9条を改正して実質的な防衛力を強化したとしても国民の負担が増えるだけで、根本的な解決にはならないような気がします。自国を防衛するための考え方が他の資本主義国と対等になっただけです。それで世界の資本主義国家間で生ずる戦火が減るわけではありません。
アフリカでは新たに独立した国家間で、いまだ戦闘が絶えません。その背景には豊かな鉱物資源の奪い合いがあります。そこにヨーロッパや中国などの、巨大企業が国家の後押しのもとに進出してきています。それがまたアフリカの紛争を加速させ、住民を苦しめています。世界の携帯電話の3割弱のシェアを占めるフィンランドの企業が携帯電話に不可欠な鉱物資源を、アフリカの犯罪組織を通じて手に入れているという情報もあります。また、原子力発電で先進的な技術を誇るフランスですが、使用済み核燃料の最終処分にはどうしても膨大なコストがかかることから、ロシアの過疎地域に搬出されて埋め立てられているという情報もあります。こうして至る所で国家の後押しのもとに企業は世界平和にとっては妥当とは言い切れない戦略を展開しています。
これが自由競争の社会、これが歴史的な現実というものであり、誰もここから逃れることはできない。こういう理不尽な現実を少しでも解決していくためには、国連などの国際機関による協調を通じて解決していく他はない。そういう言い方も可能です。しかし一方で我々日本人は、今まで同様にアメリカに軍事的に依存した状況を維持していくことで良いのかということを、あらためて考え直して見ることも必要です。沖縄問題だけではなく、領土問題や多国間貿易自由化問題など、外交面でも、いろんなほころびが出てきているのが現実だからです。
ではどうすべきなのか。私は、憲法第9条は改正するのではなく、これからはその文字通りの意味と精神を世界中に広めていくような運動を展開する必要があると思います。9条の意味するところの普及を世界的な規模での運動として展開していくようなプロジェクト。それは国家主体ではなく民間レベルの委員会のようなものを設置し、他の国々の民間レベルの団体へと働きかけていくようなものでなければなりません。日本国憲法第9条は、我々国民が自主的に他の国々へと働きかけないと、成り立たない、極めて積極的な規定として理解しなければ本来意味を持たない規定なのです。
でも、既に述べたように、そういうことは国連に任せるべきではないかという考えもあります。しかしこれも戦後の遺物として拒否権を持つ常任理事国の存在があります。国連以外で国家間の暴力を抑制する組織は可能なのでしょうか。そのためには、人類の遠い将来を見据えた戦いが必要です。今のように国家レベルではなく人々が共存できるような社会、世界中の富を貧困に苦しむ人々に分配できるシステムを持つ社会、それぞれの民族文化を尊重しあい、商品経済による等価交換ではなく、贈与的な価値を与えあうことのできる社会、そういう社会を目指した、困難で長い戦いを覚悟しなければならないことでしょう。
しかしながら再び別の声が聞こえます。そんな実現不可能な夢みたいなことよりも、現実を見据えたまえ。現代の豊かさは資本主義商品経済が築き上げてきたものだ。それを国家間の絶妙の関係が支えあっている。もちろんそこには不均衡や軋轢も生まれる。しかし資本主義国家間の進展によって我々は、今までより以上に平和と繁栄を築き上げてきたではないか。時間はかかるかもしれないが、我々はこの築き上げてきた膨大な富を、徐々にではあるが、低開発諸国の貧困に喘ぐ人々へも、国連や様々なNGO等を通じて還元してきているではないか。この我々のシステム以外に何が考えられるのだ。資本主義や国家間の支え合いを将来的に否定しようとするのは、君が何かを表明して自らの存在意義をいたずらに示したい学者か、あるいは何かに反対して優越感を持とうとする知識人に過ぎないからではないのか。
そう思われても仕方がないのかもしれません。しかし私の考えは私の知識というよりも、私の感覚に基づいています。このような社会がいつまでも続いていいものかという重たい感覚があります。グローバルな市場経済にますます飲み込まれていく社会、ある企業では企業内での会話はすべて英語でなければならないと言います。日本にあってこの異様な対応は驚きです。世界の需要を世界の隅々まで国や企業同士が奪い合うこの大きなうねりは、人類をどこへ連れて行こうとしているのでしょうか。効率と功利主義が我々を余裕のない画一化した世界へと集約していくような気がします。一部の手作業など、ある意味での非効率性を維持しても良しとする地域のまとまりや特殊性は徐々に排除されていくような気もします。問題はそのような状況を我々一人一人が分かりやすい言葉と感覚でどう捉えていけるのかということです。これは理屈以前の問題です。
30年ほど前、私が初めて沖縄を訪れた時の感覚も重たいものでした。旅行前に図書館で見た、慶良間諸島での自害の写真は衝撃でした。米軍が上陸すれば皆殺しにあうから、その前に自決しろと言う言葉を残して去っていった日本軍。残された家族たちは行き場を失った岩場でまず子供たちを殺し、親たちも首を切って自害し果てるのです。沖縄を訪れても見学した島の中部の防空壕には兵士たちが立錐の余地もなく立ったままでひしめき合い、死んでいったといいます。最後は摩文仁の丘まで追いつめられていき、兵士や住民たちの多くがそこで非業の死を遂げたのでした。
島の中央部の一等地はすべて米軍関係者の施設や住居地で、その周りに沖縄の住民の居住地が立て込んだままひしめき合っているような状況でした。当時はまだ那覇市内の国際通りなどは舗装されてはいてもでこぼこ道でした。地元住民のために整備された道路がどこまでも広がっているというイメージは全くありませんでした。人々の活気は感じましたが、どこかで閉ざされているという閉塞感を感じたものです。数年前二度目に訪れた時には、道路も格段に整備され、首里城なども復興され、観光都市としての発展を感じました。しかし相変わらず小学校の間近で米軍基地の戦闘機の爆音が鳴り響くような状況には変わりがありません。歴史的な悲劇を背負ったまま今だ、他国の軍事基地に生活が縛られているような状況が続いています。
沖縄の現状から、憲法第9条の問題へ、そしてそこから核廃絶、軍事主導廃絶の戦いへと戦いの輪を広げていかなければなりません。しかもこれらの戦いは、国家を乗り越えた民間レベルでの、非暴力の戦いとして展開していく必要があります。沖縄の現実の解決は、沖縄から米軍が出て行けば良いだけの問題ではないと思います。沖縄の問題の根本的な解決は、我々日本人がこれから背負わなければならない国際的な課題や任務をも孕んでいるということを考えてみたいと思うのです。
(2012年4月14日)
プラトンの国家(都市国家の理想的形態としての共和国)は、紀元前4世紀頃に書かれたにもかかわらず、民主主義を謳歌している現代社会にも通じる諸問題を提起しています。
私がプラトンの国家に興味を持ったのは30年ほど前の事ですが、今ここで彼の言説を整理するかたちで、国家や民主主義社会について考え直してみたいと思うのです。プラトンの国家を最初に読んだ時に興味を持った箇所は以下のようなものでした。(岩波文庫、藤沢令夫訳)
まず国家が何故生じて来るかと言えば、我々が一人一人では自給自足できず、多くのものに不足しているからだと言います。ロビンソンクルーソーのように人間社会から隔絶されている限りは、ある期間内は一人で生活できますが、人間社会のまっただ中に住んでいる限り、人々は多くのものを融通しあうしかありません。その人間社会には、様々な人が住んでいます。力の強いもの、知力に優れたもの、策略に長けたもの、虚弱なもの、意志の弱いもの等、生まれつき様々です。ですから国家の政治は、それを担うのにふさわしくない人々にゆだねたら国家は間違った方向に行ってしまう。
国家の運営を担うものは様々な訓練と試練の後にしっかりした政治哲学を持った50歳以上のものが国の守護者として、国の政治を担わなければならない。彼ら守護者達は選別されて、幼い頃から両親から離れて、無所有の共同生活を送らなければならない。家族単位の生活はなくなる。そして彼らのうちの最も優秀なる男女は、できるだけしばしば交わって、将来の国家の担い手となる、さらに優れた子供達を産んでいく必要がある。こうした優れた、選ばれたもの達が行う政治の目標は、民衆一人一人が、その生まれつきから最も適している仕事を与えられ、節制した生活と正義を実現することにある。他の国々との戦争も避けられないだろうが、国家を構成するもの全員の苦楽の共存こそ国家にとっての最大の善である。と。
家族や個人が生活の単位ではなく、特に守護者達は家族を離れた共同体の中で生活すべきだと言うプラトンの考えは、現実的な実践の事例としては、有名なイスラエルの共同体、キブツ(Kibbutu)や、日本では山岸会の事例があります。しかし個人所有を否定し、全てが平等に支給される理想的な共同体を維持していくことには、様々な困難を伴います。キブツも現在では子供の頃からの共同生活に変化が見られ、親元にいることも多いと言います。また労働に応じた賃金形態が認められているキブツもあるようです。現在の市場経済社会の競争原理とそれに伴う私有財産制を全面的に否定することはやはり難しいのでしょうか。市場経済というある種の自動メカニズムに任せているから、社会はうまく動いているという考えもあります。市場経済に依拠せずに、計画的な受給や平等の分配を選ばれた特定の人々が行おうとすると、様々な人間関係の軋轢と矛盾を生み出す可能性があります。ソ連邦の崩壊は、一部その事の現れでもありました。
プラトンの国家論を否定したヘーゲルは、次のように言っています。
「私の意志は自分のものの所有において人格的である。私は所有によって私の意志に現存在を与えるのだから、所有もまた、私のものであるという規定を持たずにはいない。このことは私的所有の必然性についての重要な教説である。」
「この必然性の例外が国家によって作られることがありうるとしても、しかし例外をつくりうるのはもっぱら国家だけである。」
「プラトンの国家の財産の共有と私的所有の原理の追放という考えは、精神の自由と法ないし権利との本性を見損なっている。世の人が財の分配に関して取り入れたいと思うかもしれない平等は、資産が勤勉次第である以上、もともと短時間のうちに壊されることになるだろう。なにしろ人間はもちろん平等であるけれども、ただ人格としてだけ、つまり彼らの占有の源泉に関してだけである。だが、私がどれだけ占有するかという問題は、平等外に属する。」
「すべての人間は生まれながらに平等であるという命題は自然的なものを概念と混同するという誤解を含んでいる。人間は生まれながらにしてむしろ不平等であるといわなければならない。」
このようにヘーゲルは、私有財産と国家の原理は、人間社会が歴史的にたどり着いた成果であり、我々の社会生活に深く浸透していると言っています。しかし彼は同時に、私有財産制や国家も人間社会にとって永遠のものではなく、将来的には人間社会の新たな形態へと変貌するものだという余地は残しています。
ヘーゲルの思想を乗り越えようとしたマルクスは、国家と市民社会、家族、は、私有財産制度と民主主義を基礎にして、一体的なものであり、共産主義社会は、そのような体制から歴史的にまさしく変貌する社会なのだと言っています。彼は言います。民主制はあらゆる体制の謎の解かれたものである。民主制はあらゆる国家体制の本質であり、社会化された人間がひとつの特殊な国家体制としてあるあり方である、と。
しかし彼の描く共産主義社会は、守護者として選ばれたものの共同生活ではなく、精神的労働と肉体的労働の分業から解放された一般人の共同生活であり、プラトンよりももっと理想的です。プラトンもマルクスも理想がまた別の意味で現実よりももっと現実的な課題を我々に突き付けているということを示したかったのではないかと思います。
プラトンは言います。
「こういう国制がいかにして実現可能なのか。我々が語ったとおりに国家を統治することが実際に可能であるということが証明できないからといって、我々の語った事項がそれだけ価値を失うと思うかね。いったい、言葉で語られるとおりの事項が、そのまま行為のうちに実現されることは可能であろうか。むしろ、実践は言論よりも真理に触れることが少ないというのが本来のあり方ではないだろうか」
特にプラトンの場合はイデアと永遠の魂の存在という考え方があります。彼の国家論は、イデアと永遠の魂が自ずから示す道筋でもあるのでしょう。
「魂には、およそ他の何ものによっても果たせないようなはたらきが何かあるのではないのか。配慮すること。支配すること。思案すること。我々の魂は、不死なるものであって、決して滅びる事がない。」
プラトンは次に民主制国家の様態を分析しています。
「たとえ君に支配する能力が十分にあっても、支配者とならなければならない
なんらの強制もなく、さりとて君が望まないならば、支配を受けなければなら
ないという強制もない。また他の人々が戦っているからといって、戦わなけれ
ばならないこともない。どうだね、この暮らし方は。当座の間は、この世ならぬ快い生活ではないだろうか。それにこの国制が持っている寛大さと、ささいなことにこだわらぬ精神、我々が国家を建設していた時に厳粛に語った事項に対する軽蔑ぶりはどうだろう。ここでは国事に乗り出して政治活動をする者が、どのような仕事と生き方をした人であろうと、そんなことは一向に気にもとどめられず、ただ大衆に好意を持っていると言いさえすれば、それだけで尊敬されるお国がらなのだ。
そして第三の階層をかたちづくるのは、民衆だということになろう。これは、自分で働いて生活し、公共のことには手出しをしたがらず、余り多くの財産を所有していない人々からなる。民主制のもとでは、この階層は最も多数を占め、いったん結集されると最強の勢力となるのだ。」
プラトンの言説からは、民主主義というものが、決していつの時代でも最良のものとはされていなかったということを示しています。それでも民衆というものはいつの時代でも多数を占め、最強の力になりうるのだと言っています。
しかしここのところは本当に難しい問題です。確かに大多数だからといって、民衆の意向のみで理想の政治を動かすわけにはいきません。優秀な人間による民衆の訓育と指導も必要です。優秀な人間とそうでない人間はいる。両方を平等に扱う事への疑問は確かにあります。しかし同時に、では誰がどのようにして優秀な人間を決めるのか。プラトンはイデアとか永遠の魂がそのような仕組みを要請するのだと言います。本来人間に備わる正義感や道徳心といったものが自ずから優秀な選ばれし者の存在を認めあう根拠となるのでしょう。だが、優秀な種を選別する事で、そうでない種の存在がまったく意味を持たない社会になっていく危険性はないのでしょうか。
しかしプラトン自身も、理想的な社会が実現されたとしても、自然の摂理によって、そうした社会もいつかは滅びると言っています。
「どれだけ支配者の知恵が秀でたとしても誤りは必ず起こる。そしてその責任は支配者たち自身にあるのではなく、宇宙全体を規制する避けがたい法則的周期から由来している。理想国家でもいつかはよき出生と悪しき出生を知り損なって劣った子が生まれてくることになり、内紛の因がかたちづくられる。これは、およそ生じてきたすべてのものは滅びというものがあるという大原則から由来し、これまで見られたような数によって規定される宇宙全体の周期的法則によって避けがたく帰結するところの悪しき出生ということから由来するのである。」と。(岩波文庫「国家」補注P415)
現代の世の中でもプラトンと同様に、理想的な社会が容易に実現できるとは思えないし、実現できてもそれは永遠には続かないだろう。それが人間社会の性(さが)なのだ、という意識は我々の心の底にも潜んでいます。
では我々はそのまま、あるがままの社会を受け入れるしかないのでしょうか。そういうことはありません。人間は現実の問題を提起し、その解決のための方策を表現し、人々にそれを呼びかけていく存在でもあるのです。プラトンに言わせれば永遠の魂のようなものが、いつの時代でもそのような存在を導いていくのかもしれません。人は生きているうちに、その人なりの主張や表現を見いだし、そのことにより、人それぞれの自己実現を図っていこうとします。プラトンは、将来の人類のあるべき姿を提示することによって、彼なりの自己実現を図ろうとしたのでしょう。それが本当に彼の師、ソクラテスの思い描くものであったかどうかは分かりませんが。
それでは我々現代の市場経済社会、民主主義社会に住む人間は、プラトンの国家の先に何を読み取るべきなのか。
現代社会の特質とは、国家の中で個々人が私的生活と私的所有を保障されているということでしょう。我々は市場経済活動によって得られた利益や賃金などの対価によって、安全と安楽な私的生活を享受することができます。しかしそれも安定したものとは言えません。企業はマスコミを利用して新たな需要を喚起し、人々には借金をしてまでも、住宅や車などを次々と購入させます。企業も増資や借金をして規模を拡大する。国も国債を乱発して公共サービスを拡充する。こうして実体経済から乖離した、虚構のマネーフローが世界中を駆け巡るのです。やがて世界中の国々で、人々の生活は同質化し、いつかは行き詰まっていかざるをえない。放漫な公共投資やマネーゲームに明け暮れた先進諸国も徐々に解決策が見いだせなくなってくるのです。欧州の経済危機から、今や世界は同時不況の入り口にさしかかっているかのようです。今我々は何を問題にしなければならないのか。
プラトンは次のように、国家と市場経済の結びつきは、人々によって作り出された生産物をどう分配しあうかを統制する事にあると言っています。
「国そのものの内においては、市民たちはそれぞれの仕事の生産物を、どのようにしてお互いに分け合うのだろうか。まさにそのためにこそ、我々は共同体を作って国家を建設した。その結果として、我々は市場を持ち、貨幣を持つことになるだろう」
そこでもう一度、先ほどの主張、つまり、社会全体の生産物の需給の調節や最終的な生活必需品の分配を適切に行える機構としては、市場経済に変わるものはない、という考えを取り上げてみましょう。市場経済はこの地球上に、有り余る富を築いてきたのは確かです。しかしその富を、あまねく世界中の人々に分配することは可能なのでしょうか。一つの可能性としては世界市場の拡大とともに、賃金の格差が徐々に解消されていくのではないかということです。例えば海外の安い労働力を求めて日本の企業は海外進出を加速させてきました。中国は既に賃金が上昇してきている。そこで東南アジアへ。そのうち東南アジアでも賃金の上昇、アフリカや南米でも。こうしていつかは企業の海外進出もメリットがなくなってくる。その段階で市場の自己調節機能は全世界の人々に富を分配しあえるような結果をもたらすことができるのかもしれません。
しかし上昇した賃金の中身はどうなのか。市場が供給する奢侈品に眼が奪われて、ますます長時間労働に明け暮れるのでしょうか。また海外進出で利益を上げた企業は、相変わらず自己増殖を図って、地球上の限られた資源や需要を奪い合うことはないのでしょうか。そのような堂々巡りがいつまでも続くようなら、やはりプラトンやマルクスのように、新たな社会形態の概念を考えだしていく他はないのでしょう。しかし考えだされた理想や理論だけですぐに人間社会が変貌するものでもありません。どこかでその理想の実現に向かって人々を引っ張っていく人格が現れなければならない。だが、グローバル化した世の中だからといって、国連や国際会議の場で、そうした人格が活躍できるとは思えません。むしろ小さな村や街、あるいは何処かの都市でそのような人格が登場し、その評判が全世界に広がっていく形で新たな社会への変貌は時間をかけて進んでいくのでしょう。
そうした人格が現れたとしても、プラトンの言うように、一人の人間の一生は宇宙の膨大な時間に比べたら、すぐに消えてしまう一生に過ぎません。それでも、ほんの一瞬の一生を携えて、理想の社会への実現に向けて、一歩を踏みだそうとする人格は、いつの時代にも存在します。それこそ、プラトンの言う、永遠の魂の仕業だということになるのでしょうか。
(2012年6月24日)
認知症を患っている父を看病しながら、この病気について書いてきました。
私が最初に父の認知症について書いた時に比べて、父の症状はずいぶん悪化してきました。犬の散歩はできない。畑仕事もできない。寝るだけの時間が多くなりました、。しかし自分では散歩も畑仕事もしているつもりなのです。何度も学習させたら、新しいことを覚えられないわけではない。しかし一時するとまた昔の記憶の習慣に戻ってしまう。何かを学習して覚えるという思考パタンは、当然生きるために必要なことであり、昔からの習慣としても心の中に残っているのですが、それがもはや新しい知識として蓄積されないのです。
母が亡くなる前は、四六時中冷蔵庫を開けて、果物や甘いものを口にしていたので、今でも冷蔵庫の中をあさり、卵やハム、リンゴ、パンなどを入れてある鍵をかけた箱を壊して、中のものを食べたり、箱はどこか我々にも分からないところに隠すのです。隠すということは、行為を行った時には、自分でもまずいと思ったのでしょう。だが、私が後で注意しても、自分で何をやったかはまったく覚えていないのです。そんなおり私は父が認知症だと分かっていても、声を荒げて怒ることがあります。そして怒った後は、父に対しても、そして自分に対しても何とも情けない気持ちでいっぱいになります。その他にも、ここで書くこともはばかられるような、認知症故の様々な失態は数えきれない程あります。
それでも私は声を大にして言いたいのです。認知症は病ではあっても、我々が死に向かって誰もがたどる道筋への先取りでもあるのです。脳が活性化する機会を与えてやるべきだと言いますが、しかし何故にそう最後までやたらと活動しなければならないのか。もし病気ではなく、老衰で死ぬとしたら、脳はいつまでも活性化しているのでしょうか。そんなのもういい加減にしてくれと言いたくなります。人間は突然死ではない限り、脳が徐々に不活性化して死に至るのです。認知症は、根本的には、薬や、食事や、運動等では解決できない、人間の、いや動物の構造的な営み、鉱物でも植物でもない動物の必然的な歩みの、一つのあり方だと思います。
いい薬が出た、こういう食事の取り方で、こういう運動で、といった対処法は、少しは改善するにしても根本的な解決にはならないのです。デイサービスや老人会など多くの人と交わり、話をすることで、確かに脳は一時的には活性化します。しかしそれとて本人にとっては、もういい加減にしてくれ、私は一人でゆっくり休みたい、もうあまり他人と話したくないと思うかもしれない。そうなればもう何も悩みはない。もう外部との緊張関係は必要ないと、判断すれば、判断というか、そういう意識下の指令が出されれば、そうするしかない。ボケはそういう意味でその人に与えられた、一つの個性と言ってもよいのです。ボケはボケなりにこの世との関係を変化させて、あの世へと向かう方法なのです。ですから最近マスコミで話題になっている医学的療法やリハビリには、元々限界があるということを知っておく必要があります。
そうはいってもますます多くなるであろう認知症患者の増加は、介護する側の大きな負担であり、社会にとっても大きな問題です。日本だけではなく、特に先進諸国の老人の間で、患者はますます増加しているようです。私の父は、もうすぐ90になります。戦時中軍隊で九死に一生を得ながら終戦を迎え、勤務先を転々と変えながらもやがて地方銀行に居場所を見つけ、そこで働き尽くめの生活を送ってきたのでした。しかし退職時には生活にも余裕が生まれ、夢であった海外旅行にでかけることができました。ツアー旅行に参加して、世界的な観光スポットをほとんど見て回ることができたようです。その後九州の家を売り払って、母と一緒に千葉の我々の家族と一緒に住むようになりました。そこで10年以上、畑で野菜などを栽培しながら、悠々自適の生活を送ってきたわけですが、三年ほど前から認知症の症状が現れてきたのでした。
先進諸国では、お金さえあれば何でも享受できるような世界が築き上げられてきました。人間の欲求を満足させる様々なパタンは、テレビや雑誌などのコマーシャルを通して、人々の心の中に浸透していきます。様々な電化製品をそろえたマイホームや海外旅行を夢見て、多くの人々は一生懸命働き、財産を築いてきました。そしてそれらをある程度実現し、家族も平和で、孫も生まれて、安泰な生活に到達すると、いつのまにか気力と記憶力が急激に弱まり、自分の老いを実感させられるのです。そして、もう、お金でまかなえる飽食と享受だらけの世界には即座に反応できなくなっていきます。
お金をためて、好きな人と結婚し、家を建て、家財道具や電化製品をそろえ、最新の車を購入し、おいしいものを食べ、家族と旅行にいく、そうした生活は誰でも夢見ることであり、それはそれで今の世の中を動かしている要因の一つです。しかし、面白いことに、認知症の患者は急にお金に無関心になるのです。私が知る限り、身近な認知症患者は皆そうです。口ではお金が全てだ、お金があるから何とかやって来れたと言いますが、その一方で、お金の管理は一切出来ないどころか、無関心になるのです。お金の計算が面倒になるということもあります。しかし根本は、もはやお金がいっぱいあってもどうしようもないという気持ちがあるからでしょう。そんなところにいつまでも本来の自分の居場所はないのです。テレビを見てもあまり楽しめず、ほとんど寝ている父は、ある日、テレビでアフガンの貧しい農村の子供が毎日麦の粉を練ったようなものばかり食べているドキュメンタリーを見て、久しぶりに微笑んでいました。なんだかアフガンの子供の姿に自分の幼い頃の貧しい姿がだぶってきて郷愁を誘ったのかもしれません。
父の子供の頃の村や町は、どこの家も開け放たれていて、通りの往来を眺めることが出来ました。荷馬車が通り、子供達が通り、若者や娘達が通り、老人達は家の中から、そうした往来を眺めて過ごしました。老いてもそれなりに、隅っこに自分の居場所がありました。現代の老人達も、そんなゆとりと郷愁の世界にいつかは戻りたいと思うのかもしれません。
しかしながら、テレビの中で、アフガンの子供の父親は、子供達が大人になっても、このような貧しい農家の生活をさせたくはない、我々は学問がなかったから、こういう生活しか出来なかった。だが子供には、なんとか学校に行かせて、都会に出て出世してもらいたいと話していました。だが、毎日粗末な同じ味のものばかり食べているアフガンの少年にとって、毎日おいしいものが食べられる生活とはどんな生活だと想像できるのでしょうか。飽食でがんに冒されて、薬を一杯飲んで、様々な医学的処置を繰り返されて死を回避しようとしている人間の世界を信じることが出来るのでしょうか。
こうして認知症が増加していく原因の一つは、どこまでも需要を喚起し、ものを売りさばいていく、巨大な商品経済社会の行き着くところにあるようにも思えてきます。そうした中で、人々は、テレビやグルメや旅行や快適なマイホームを実現して楽しんでいる。あるいは実現しようとして毎日朝早くから夜遅くまで働いている。そこには常に充実した未来への展望があり、老いや死についての観念は入るべき余地もない。企業は競い合って新たな医療技術や薬を開発して、老いや死を出来るだけ遠ざけようとします。しかし人間は誰でもいつかは老い、そして死に至る存在です。自分が老い、死んでいく場所を徐々に確認していく存在です。ところが地球の果てまで広がる巨大な商品経済の進展はそれを許さないのです。老人達の多くは、この情報化社会の中で、孤立し、自分の居場所を見失って、認知症という病名だけが与えられていく存在へと変貌していくのです。
こうした事態は、人間のあるべき生き方と死に方が問われているということでもあります。また、ある意味で人類の未来をも示唆するものなのかもしれません。物忘れをしないでどうして人間は充実した一生を終えることができるのか。いつまでも脳を活性化させるのなら、人間という動物は狂ってしまうことでしょう。長生きしてもたかが知れています。人間はいつまでも元気で長生きがしたいのでしょうか。いつまでもということはあり得ません。人間は、いつかは、どのようにして死に至るのかを考え、自分にとって、今まで生きてきた時間とは何なのかを考える存在です。一人一人が老い、死に近づくにつれて、こうしたことを考えるのが人間の本来の生き方ではないのでしょうか。
アフガンの少年のように、麦粉を練ったようなものを毎日食べて生活している少年は、未だ世界中に存在します。彼らの一部はやがて都会に出て、贅沢な生活を誘引させる企業間の競争の担い手となって、働きずくめの生活を送ることになるのでしょうか。このような生活がいつまでも続くのが我々人間社会というものなのでしょうか。それともまた違った世界の可能性が残されているのでしょうか。昔はもっとゆったりとした時間が人々の心の中にあったような気もしますが。これだけ急速に技術が発達して、世界全体の富の蓄積が増大しているのなら、そろそろ何か工夫をすることによって、世界中の富が全人類に効率的に分配できるようなシステムを構築しはじめていくことは不可能なのでしょうか。先進諸国で進行している高齢化社会と認知症患者の増大、一方で世界中で相変わらず進行している貧富の差の拡大を目の当たりにして、我々は様々な思いを巡らさざるを得ません。
この記事で一応、このWhat’s New の窓口での記事は終わりにします。後はLife of Tara, や「やまぼうしブログ」で私の近況は綴るとして、まとまった考えは、新たに、「時間について」や「タラから南インドへ」のページで語っていきたいと思います。
(2012年10月23日)