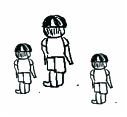Top タラの芽庵注解 本文( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 )
タラの芽庵便り
大木邦夫
1 タラの芽庵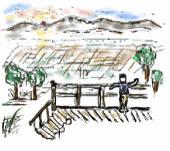
タラの芽とは、あのタラノメです。春先、若芽を天ぷらにするとおいしい、木にいっぱいとげのある植物です。それが所々に自生している、房総の、とある小高い丘の牧場にタラの芽庵という名の丸太小屋があります。作業部屋と囲炉裏のある部屋、そして四五人ほど寝泊まりのできる屋根裏部屋もあります。私は週末になると、自宅から車で小一時間ほどかかるこの庵に訪れます。そしてのんびり房総の山々のなだらかな稜線を眺めて過ごします。夕暮れ時、大空は夕焼けからだんだん暗くなり、山の稜線はかすかにしか認められなくなります。この大いなる空間にまるで時間がとけてしまうかのように、じっと山並みを見つめるひとときは、もう何も考えず,私自身もとけてしまいそうな気がし
ます。
タラの芽庵は大きな丸太を組み合わせた山小屋です。私一人では造れません。当時の組合長、佐藤さんに土地や資金の協力を得て、十数人が会員として集まって20年ほど前に造り始めました。週一二回の作業なので完成に5年ほどかかりました。完成当初は家族同士で集まって楽しく過ごしました。牧草地で陸稲を作ったり、味噌を作ったり、いろいろな料理を作ったり、ここでみんなといろんな活動をしました。
しかし、みんなで集まることはだんだんと少なくなってきました。多くの会員はここまで来るのに私よりずっと時間がかかります。子供たちも大きくなり家族では来ることができなくなりました。また会員自身も仕事や家庭の用事に追われて、なかなかここへ来る時間が見出せません。それに、組合長の佐藤さんも、奥さんも病で亡くなりました。組合の酪農家も現在営んでいるのはわずかで、酪農団地としては閑散としています。今となっては朽ちかけてきた部分の修復をもかねて、タラの芽庵を訪れるのは、ほとんど私だけになりました。月日のたつのは本当にあっという間です。
でも、人々はいなくなってもタラの芽庵の床下には大きなウシガエル、裏山には郭公や鶯が迎えてくれます。スズメバチもタラの芽庵の住人を知っているかのように、楽しくタラの芽庵の周囲を舞うだけです。会員が書籍を持ち寄った本棚の裏からは蛇の脱皮した抜け殻が出てきます。一昔前は大勢の犬や猫たちもいました。ナチという大変利口な犬もいましたが、みんなひっそりとどこかに隠れていなくなりました。それでもここへくるとなんだかひとりぼっちだという気がしないのです。タラの芽庵の維持管理に一汗も二汗もかいてしまいますが、遥かな山並みから吹き抜けてくる風も、風に舞う木々の緑も、小鳥の鳴き声も、ここではとても心地よく感じます。
2 生き物たちの戦いと精霊
昨年の暮れだったでしょうか、いつものように週末、タラの芽庵を訪れると、なんだか様子が変です。入り口前の ベランダに大きな雉子の死骸が横たわっていました。窓の網戸は引き破られ、窓ガラスが倒れかかっており、周辺には無数の羽が散らばっていました。食いちぎられた内蔵の血痕はまだ生暖かいようで、つい先ほどここで壮絶な戦いがあったことを連想させました。相手は何だったのでしょうか。大鷹なのか、何かで傷ついていたところをイタチに襲われたのでしょうか。部屋に入ると囲炉裏の灰の中には、雀の死骸も見つかったのです。雀までもが倒れた窓ガラスの隙間から必死で中に入ってきたということは、やはり猛禽類が襲いかかったのでしょうか。まだどこかから叫び声が聞こえるような、血がほとばしるような生々しい雰囲気に襲われたのを覚えています。
ベランダに大きな雉子の死骸が横たわっていました。窓の網戸は引き破られ、窓ガラスが倒れかかっており、周辺には無数の羽が散らばっていました。食いちぎられた内蔵の血痕はまだ生暖かいようで、つい先ほどここで壮絶な戦いがあったことを連想させました。相手は何だったのでしょうか。大鷹なのか、何かで傷ついていたところをイタチに襲われたのでしょうか。部屋に入ると囲炉裏の灰の中には、雀の死骸も見つかったのです。雀までもが倒れた窓ガラスの隙間から必死で中に入ってきたということは、やはり猛禽類が襲いかかったのでしょうか。まだどこかから叫び声が聞こえるような、血がほとばしるような生々しい雰囲気に襲われたのを覚えています。
太古の人類は、このような場面に何度も遭遇したことでしょう。襲われる動物たちや襲う猛獣や猛禽たちの中に彼らは何を見たのでしょうか。襲われると死ぬということ、襲ったり、襲われたりするのも生の営みの一部分だということ、また生を営むためには安全を確保しなければならないことを感じ取ったことでしょう。こうして人類は他の動物と同様に、安全な場所や食料を確保したりして、生き延びてきました。
他方で人類は他の動物たちよりも広い心の世界を持っていました。心の世界を持つことによって、人類には死と同様に安全も自分の力の及ばない範囲から贈られるものかもしれないという思いがありました。そのような思いは、人類がものや現象の背後に横たわる精霊のようなものと出会い、それを敬うようになったことにも表れています。人類ははるか昔から猛禽や猛獣の仮面をかぶって精霊を鎮める祭りを営んできました。精霊を媒介として、自分たちの安全を集団として維持してきたようにも思えます。
私たちの祖先は、精霊とは、人類の生死をも左右する力であり、それは善であることも悪であることもありえると考えました。バリ島の伝統芸能バロン劇では人類や動植物、あらゆる生命を含めて、善と悪の精霊の絶え間ない戦いがこの世の中だということを表現しています。バリ島のヒンズー教では悪の存在がその教えの大きな要素になっています。最後は善が勝利を収めるにしても、動物のみならず、人類も含めて善と悪が共存する世界で戦うこと、それが生き物の世界、我々の世界の生だと教えています。なんだか恐ろしい考えですが。
生き物といえば、シロアリや木喰い蟻にも悩まされています。タラの芽庵の中に入ると、床のどこかに細かい木屑が山のように盛られているのです。おいおい待てよ、といってもそのままでは丸太が食い荒らされてしまいます。腐食した部分をチェーンソーで削ってコールタールをたっぷり塗った丸太切れをそこに打ち込むのです。チェーンソー、この文明の利器はたいしたものです。ウッディライフといっても、斧や鋸だけでログハウスを造るのは大変です。実は気がつかない間に裏山の大木の枝がタラの芽庵の屋根までぐんぐん伸びて、みしみしと屋根を押しつぶそうとしているのです。こんな自然の恐ろしい成長が、一人だとなかなか気がつかないものですね。直径10センチ近くもある太い枝々を屋根に登って切断するには、おっ かなびっくり、斧や鋸だけでは大変な作業です。チェーンソーのお陰であっという間に処理できました。
かなびっくり、斧や鋸だけでは大変な作業です。チェーンソーのお陰であっという間に処理できました。
しかし直径20センチの丸太で組んだタラの芽庵は、もともとは頑丈で、時折大きな台風の風をまともに受けてもびくともしません。
植物が絡みつき、動物が住みつき、動物たちが戦い、人間が訪れ、人間が植物や動物たちと戦い、こうした中で苔むしたタラの芽庵も生きてきました。
3 牧場の組合長、そしておばさん
冒頭でお話しした通り、タラの芽庵の建設は20年前に始まりました。当時牧場組合長の佐藤さんも50代半ばの働き盛りで、酪農経営の合間をぬって、我々と一緒に建設作業に従事していただいたものです。佐藤さんの奥さんは肺がんで亡くなりました。どこかの良家のお嬢さんだったらしいのですが、色男の佐藤さんに惚れ込まれて嫁いだものの、三人のお子さんを育てながら酪農に従事するという重労働に明け暮れたのでした。それでもけろっとした明るい性格で、作業中の我々に昼のおかずを運んでくれたりしたものでした。その後子供たちは成人し、外に出てしまい、夫婦二人だけで36頭の乳牛を飼う酪農の仕事はあいかわらず大変でした。24時間牛の世話をしなければなりません。えさをやり、乳を絞り、こまめに牛舎を掃除したり、牛のお産の介添えをしたり、そんなこんなで毎日が過ぎていきます。おばさんは牛に押しつぶされて大けがをしたこともありました。それでも私たちが家族を連れてタラの芽庵を訪れると、すぐ近くの牛舎に隣接して住んでいるおばさんはいつもにこにこと迎えてくれたものでした。本当にかわいいおばさんでした。
いまから9年前の冬のことでした。いつものように牧場を訪れると誰もいないのです。数日前はいつもの調子で元気だったおばさんもいないのです。書き置きから入院している近くの病院に急ぎました。佐藤さんと娘さんが付き添っていました。おばさんは危篤状態で、酸素吸入器をつけてはあはあしていました。もう誰も認識できなかったらしいのですが、佐藤さんが、私がきたよとおばさんの耳元でつぶやくと、急に頭をもたげて私の方を見て「アーッ」といって何かしゃべろうとしたのです。佐藤さんや娘さんは、ああ私のことが分かったんだと言いました。最後の別れでした。肺の重篤な病でした。時々風邪気味だと休んでいることもあったのですが、ああ、ここまで我慢されていたのかなと深い悲しみに襲われました。
それから佐藤さんは酪農もやめて一人で生活するようになりました。急にやめたからか腰が曲がり、足も弱ってきました。牧場を訪れたときは弁当を差し入れして、四方山話をするのです。部屋には一匹の猫が住み着いていて、普段の佐藤さんの話し相手になっているようで、猫と話すと、ぼけなくてよいと言っていました。でもおばさんのことが話題に出ると、時折あの大きな体を揺すって泣き出すのです。
一時ヘルパーさんに週二回ほどきてもらって生活していました。その佐藤さんも今から六年前の冬、自宅前の庭で倒れたりしたこともあり、その後数年間、東京の娘さんのところに居候しました。東京はこちらよりも老人福祉が充実しているようで、リハビリに出かけたりして元気に生活していました。向こうで多くの若者たちとも交流していたようです。しかしどうしても牧場に戻りたいらしく、牧場に戻ってきました。ところが一人暮らしの不摂生からか、再び足の具合が悪くなり、いっとき病院に入院していました。それでも牧場に戻りたがり、車椅子を使って生活することになりました。しかし牧場に帰ってからまもなく体調を崩してしまい、亡くなりました。二年前の暮れのことでした。タラの芽庵をみんなで建て始めたころ、まだ50代だった佐藤さん夫婦も80代に達する間際で相次いで亡くなったのです。
こうしてタラの芽庵の近くにある組合長夫婦の住まいは、もう誰も住んでおらず、周辺の草木はのび放題になります。タラの芽庵を訪れる我々や、近くに住む佐藤さんの長男家族が周辺を時折管理して、このすばらしい環境を守ろうとしています。しかしそういう我々もあっという間に歳をとってい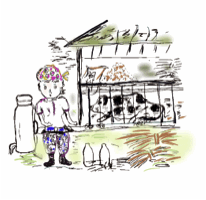 くのです。
くのです。
ところでおばさんに悪いことをしたと思うことがあります。それはおばさんがアシナガバチにさされた時、タラの芽庵においてあったアンモニアをとっさに塗って助かったという話を聞いた時でした。ああよかったですねと答えたのですが、本当のところアンモニアは効かないらしいのです。それでもおばさんは私たちがタラの芽庵に到着するとすぐに飛んできて、本当に助かったと喜んでくれた笑顔の輝きが今もって忘れられません。
4 死者の書とヴェーダについて
タラの芽庵から眺める大いなる落日を前にして、私は時折、民俗学者で歌人の折口信夫が書いた小説「死者の書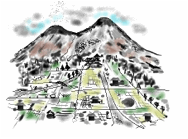 」(注1)を思い出します。
」(注1)を思い出します。
奈良時代、それは藤原氏が実権を握っていたころ、今からおよそ1300年前のことでした。藤原南家の郎女が二上山に落ちる夕日に西方浄土の阿弥陀如来を見出すというお話です。二上山は大阪と奈良の境界、当麻路に位置し、二つの峰をもつ優美な山です。そこには政略によって、非業の死を遂げた、英雄大津皇子が葬られています。南家の郎女は彼の霊と阿弥陀如来が重なりあった心象を二上山の峰の間に沈む落日に認めるのです。そして、ついに彼女はその夕日に向かって失踪します。
私はこの物語を思い出すと同時に、タラの芽庵から眺める山並みの真っ赤によどみ輝く稜線の彼方に、西方浄土を思います。そして西方浄土を越えて、私の思いは仏陀が最初に教えを説いたインドのサールナート、さらにはインドを南に下って仏陀の考えを育んだと思われるヴェーダの故郷、ドラヴィダの村々へと広がっていきます。
インダス川流域に住んでいたドラヴィダ人は紀元前のはるか大昔、インドへのアーリア人の侵入に押されて南下し、現在の南インドへと辿りついたのでした。そしてそこでヴェーダの教えを深め独特の世界を形成してきたのです。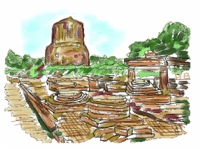
二年前の夏、わたしはインドを訪れました。サールナートからドラヴィダの村々へと南下し、ヴェーダの教えに触れる機会を得ることができました。最初にサールナートでは、博物館で有名な青年の仏陀坐像を見ました。それは溌剌として、知的で、人類への信頼と道徳的な啓蒙への意欲、すなわち善的なものへの信頼にあふれたものでした。しかし私はそのような青年仏陀座像の端正さの向こうにある問題、善と悪のめくるめく深遠の世界に入り込む思想、仏陀がたどり着いた教えの背景にあり、また仏陀が深く学んだと思われるヴェーダの教えを求めてインドへ旅したのでした。(注2)
私はサールナートから南へ下りました。私が訪れたドラヴィダの村の言語は主にタミル語です。昨年亡くなられた国語学者の大野晋先生はタミル語が日本語に与えた影響を研究されました。タミル語は大陸や海を経由して我々日本の文化や言語に大きな影響を与えてきたというのです。私はドラヴィダの村にあるヴェーダの教育施設で最高指導者であるアーチャリアに会うことができました。彼はタミル語で話しましたが彼に仕えるグルが英語で通訳してくれました。(注3)
その折、私がアーチャリアから教わったことは、私たち人間一人ひとりの人生が永劫の過去から未来へと歩む人類という大いなる作品に連なっているのだということでした。高貴な人間も、下賎な人間も、強者も弱者も、人格者もならず者も、善人も悪人も、そのときの時代が生み出す人類という作品です。時代が生み出すとは、永劫の過去からの血と肉を我々は受け継ぎ、背負っていかざるを得ないからに他なりません。ヴェーダでは、「この肉体は、父母の垢穢より生じたる垢肉なり」(注4)と断言します。人間はこうした過去のしがらみから逃れることはできません、同じような業に取りつかれ、同じような戦いを繰り返していきます。しかしそれでも人間が向かうのは未来です。未来に向かって新たな過去を築いていきます。だから我々は作品なのです。めくるめく輪廻が生み出す作品です。ヴェーダはこうしてこの世の初めから、この地球上に張り巡らされていた教え、人類の智慧なのです。

ところで折口信夫の「死者の書」は、墓に眠る大津皇子の屍がぶつぶつと話し出す場面から始まります。屍は彼が自害させられる前に出会った、どうしても心の中で消すことの出来ない姫君への思いを語ります。それは一度きり見た顔、彼が自害した磐余の池で彼をいとおしがっていると思えた藤原鎌足の姫君の顔でした。彼の屍はそもそも自分が誰かを思い出せないまでも、彼女の顔は、ありありと思い出すのでした。それは「明るい意思」となって、彼の墓を飛び出して二上山を彷徨います。
南家の郎女は当麻の語り部の老女から二上山に眠るこの大津皇子の話を聞きます。当時権勢を誇る藤原一族の娘であったこの聡明な郎女は、二上山のふもとの当麻寺で阿弥陀経の千部手写を終えます。そして手写でやせ衰えた身を振り絞って二上山を仰ぐと、彼女はそこにありありと荘厳な人の面影を見出し、無上の歓喜を覚えるのです。
この物語で折口信夫は、時代は隔たりながらも、ある優れた人格を通じて、連綿と続く人類の精神の営みの連続性を表現しています。南家の郎女は当麻の語り部から、大津皇子の魂は、同じく非業の死を遂げた太古の英雄たちの魂を受け継いでいると聞かされます。彼女は過去の偉大なる人格の魂と出会い、それが仏の魂と一体となって、彼女を更なる人類の未来へといざなっていくのです。こうした偉大な人格に対する彼女の思いは未来へと何かを志向する私たちの思いにも連なっていくように思えます。
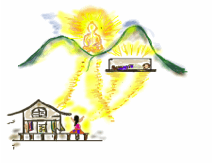
大津皇子が藤原鎌足の娘に引きつけられ、また南家の郎女が大津皇子の霊に縛られたように、現実に生活する私たちにとっても、何故に、自分は、このような特定の人格と出会い、そこに縛られるようになったのか、と思わざるを得ないことがあります。ヴェーダでは、これらの思いは人間の心に潜む、アートマンの仕業だと説明します。ヴェーダは言います。「ああ、あらゆる愛しいものは、愛しいものなるが故に、それを愛するものにとって愛しいのではない。そうではなくて、それを愛するもののアートマンのゆえに、愛しいものが、それを愛するものにとって愛しいものとなるのである」と。(注5)
難しい言い方ですが、アートマンの仕業だということは、大昔から連綿と続く人類の願望や欲求を、それが善であれ、悪であれ、我々一人一人がそれを個別に背負い、生きていくということではないでしょうか。しかしそのことは過去のしがらみに押しつぶされてしまうということではあ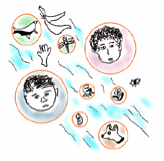 りません。我々の持つ、願望,希望、期待,憧れには、明らかに未来へ向かって何かや誰かを志向し、その何かや誰かをこちらへと引き寄せる作用があります。ふとした日常の出来事の中にも、そうした作用が現れることを我々は知っています。しかしながら我々がお互いを引き寄せあい、何かを成就するという確証はどこにもないのです。誤解や行き違いが世の常でしょう。
りません。我々の持つ、願望,希望、期待,憧れには、明らかに未来へ向かって何かや誰かを志向し、その何かや誰かをこちらへと引き寄せる作用があります。ふとした日常の出来事の中にも、そうした作用が現れることを我々は知っています。しかしながら我々がお互いを引き寄せあい、何かを成就するという確証はどこにもないのです。誤解や行き違いが世の常でしょう。
それでもこうした志向を通じて、私たちは他者や、出来事、事物を理解し、関係しあうことができるように思います。そして相手も同じように何かを志向して、何かを引きつけようとしている。各々がそのような錯綜した道筋をたどることによって人はやがて各々の道筋そのものを理解し、死に向かって受け入れるべき何かを理解しようとします。われわれは限られた生ではあっても、我々一人ひとりが抱くこのような志向の不可思議によって、我々の生活を少しでも未来へ向けて形作っていくことができる。そう思います。
5 カフカの城と世間という掟について
もう一つタラの芽庵で考えたことをお話しさせてください。それは世間というものについてです。世間とはまさしく私たちが生きているこの世の中です。前の章で私は、「我々がお互いを引き寄せあい、何かを成就するという確証はどこにもないのです。誤解や行き違いが世の常でしょう。」と述べました。世間とはまさしく「世の常」として、私たちが何かを志向し、そこで表現し合う場所、噂とか評価、批判がお互いに了解し合える場所、端的には新聞、雑誌やテレビなどのマスコミを通じてそれらを了解し合えるような場所のことです。この世間の中で私たちは意気揚々と戦い、あるいは惨めに敗北し、勝ち負けにこだわり、反社会的な立場を取ったり、社会の中で賞賛されたり、さげすまれたり、名誉欲を満足させたり、社会の底辺で押さえつけられたりして生きています。
私たちは一般に世間というものを自分から対象化して考えています。世間とはこういうもの、ある意味で俗なものだと。そこである人々は世間に逆らわず、世の中をうまく渡り歩こうとします。またある人々は逆に反世間的な価値観を研ぎ澄ませ、こうした社会を変革しようとします。しかしどのような世の中になろうとも、私たち人間が社会的人間として生きていく限り、私たちは宿命としての世間から逃れることはできません。これは先ほどお話したヴェーダの教えともつながります。すなわち過去から連綿と続く人類という作品としての世界が端的に現われるのがこの世間だからです。
変革してより自由になったと思われる世の中だとしても、どこにでも権力は生まれてきます。自己承認の欲求や表現欲は人間社会の個にとっては必要不可欠な欲求です。いつの時代でも名誉欲や権力欲、自己優越感は消えることはありません。そこから偉大な業績が生まれる場合もあるでしょうし、逆にごますりや陰謀、偽善的な策略を生みだすこともあるでしょう。
何かを表現し、他人に認めさせようとする人間の存在、あるいは人間性そのものがある種の表現的な暴力、権力を宿していることになるのでしょう。私たちはそれとは気づかずとも日常生活での何らかの立場をとって、普段何らかの権力を行使しているのです。といって、こうした表現の権力性を否定したのでは、人類は未来に向かってなんら文化的な創造をなしえなくなります。例えば、ある人々は市場経済や国家とは無縁の新たな人間社会の構築を模索すべきだと主張します。地球上の富の分配の不均衡を、国家に頼らない活動の中で明らかにし、そうした中で国家にかわる社会的枠組みのあり方を問いただしていくべきだと。そのような考えを世の中に広めようとすることは、十分新たな文化的創造を予感させます。事実、そのような表現活動に真摯に従事している人々の存在は、私たちに対して、この社会でただ安穏と生活するわけにはいかないのではないかと考えさせてくれます。
実際にアジアやアフリカで国家に頼らず、農村集落の生活の復興を援助している海外ボランティアがいます。そうした活動に参加する限り、重い責任と限られた生活の拘束、人間関係の軋轢は覚悟しなければならないし、彼らはそこから多くを学ぶことができます。そして彼らは学んだ成果を学会やマスコミに発表することによって、我々にも多くを教えてくれます。しかし、そうした広がりは更なる活動の推進力になると同時に、世間というものから一方的な賞賛や誤解を得るという誘惑や危険にもさらされることになります。
他方で世間にはそうした発表や知識の世界とは無縁の多くのもの言わぬ人々が存在します。一昔前、まだテレビのない時代、日本の多くの農村では日々の労働の合間には、ゆったりとした休息が保たれていました。農民は薄暗い母屋の開けはなれた土間から田んぼや川原の土手など、遠くをじっと見つめてそのような時をすごしました。そこで彼らは毎年同じように田植えや稲刈りなどのこれからの仕事をもの言わぬまなざしで算段しているのでした。
こうしたもの言わぬ人々の労働と日々の暮らしは、いつの時代にも多くの人々を支えてきました。カフカの小説、「城」では、アマーリアという娘が上級役人の愛の欲求に答えなかったというだけの、いわれのない罪で村からのけ者にされていく消防士の一家の破滅を描いています。外部から村にたどり着いた主人公Kは、何故役場の上層部に無実を論理的に訴えられないのか,そのような自由を行使しないのかと最初は彼らに対する優越感を持って考えます。しかし、彼はそのうちそのような知識や優越感だけでは解決できない掟、日常生活を守りぬく人々に潜む途方もない人間社会の掟に直面するのです。主人公Kはアマーリアの姉オル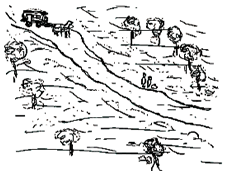 ガから、もの言わぬ両親の不毛な戦いを聴かされます。
ガから、もの言わぬ両親の不毛な戦いを聴かされます。
「まわりにはただ灰色の雪と霧の他に何もなく,見渡す限り、そして何日も、人間一人、車一台通らないのです。そこに両親は毎日訪れ、身体をほとんど包んでくれない薄い毛布をかけてうずくまって無実の罪を許してくれと乞うために、そこを通るかもしれない役人を待ち続けるのです。なんと言う光景でしょう、K、なんと言う光景でしょう!」(注6)
権力からの仕打ちを受けても、自分たちの生活を支える権力そのものは否定できない、それどころか自分たちの生活を守るために権力へ乞い願うしかない人々、また乞い願うことを拒否しても毅然として耐えているアマーリアの姿に、Kは社会を、世間を形成し、そこで生きていく人々を支えている言いようのない力を認めて呆然とするのです。
「アマーリアはたくさんの重荷を担っていただけではなく、それらを見抜くだけの頭を持っていたのです。私たちは結果だけを見ていたのにあの子は原因まで見抜いていました。私たちはちっぽけな手段を望んでいたのに、あの子はもうすべてが決定されているのだということを知っていました。真実と面と向かい合って立ち、生き、そして、そうした生活を今と同じように、あのころも耐えていました。」(注7)
オルガの話を聴いているうちに、Kは「彼にとってはあまりに大きな、ほとんど信じがたい世界が開けてきたので、Kは自分の小さな経験でその世界に触れ、その世界の存在と自分の存在とをいっそうはっきりと確認したいという気持ちを捨て去ることはできなく」(注8)なります。
こうして主人公Kは、権力に立ち向かおうとする自分、意思の自立と自由を維持していると確信している自分が、逆に小さく見えてしまうのです。
人々は様々な重荷を負ってこの世に存在し、人間社会の深淵を支え合っているかのようです。私たちの自由さえをも支えているかのような語り得ないものが、私たちの社会や世間そのものに内在しているような気がします。それは私たちを安心させ、豊かな表現欲求を開花させる場所、自由を謳歌させる場所をかたちづくる力であると同時に、また私たちを途方もない深淵の無に突き落とす無慈悲な力でもあるように思えます。
先に述べた通り、私たちはそれぞれ過去のしがらみを背負いながらも、未来へと向かっていく存在です。しかし世間というものに囲まれた私たちの生活、そしてそういうものが突然失われた暁の、なんともいえない無、そういうものをちゃんと理解しないと未来に向かって何か本当のことはできないような気もします。
6 神秘との出会いについて
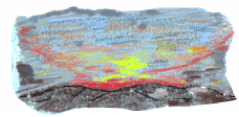 夕方、タラの芽庵から眺める房総丘陵に太陽が沈むと稜線が赤く染まり徐々に暗くなっていきます。そして夜の帳が降りてくると、今度は稜線がボーッと輝きだすのです。東京湾からの明かりが届くのかもしれません。私は作業で疲れた体をベランダに横たえて、こうした一連の変化を、ただただ眺めてすごします。虫の音や牛舎から時折流れるモーターの音を聞きながらゆったりと時が流れていきます。何も考えず、何もやろうとはせず、ただただぼんやりと気持ちよく時が過ぎていきます。
夕方、タラの芽庵から眺める房総丘陵に太陽が沈むと稜線が赤く染まり徐々に暗くなっていきます。そして夜の帳が降りてくると、今度は稜線がボーッと輝きだすのです。東京湾からの明かりが届くのかもしれません。私は作業で疲れた体をベランダに横たえて、こうした一連の変化を、ただただ眺めてすごします。虫の音や牛舎から時折流れるモーターの音を聞きながらゆったりと時が流れていきます。何も考えず、何もやろうとはせず、ただただぼんやりと気持ちよく時が過ぎていきます。
少年時代、私は九州の片田舎で育ちました。田んぼの真ん中の一軒家に家族で間借りしていました。夏の夜、母と歩いた田んぼのあぜ道には蛍が飛び交い、数匹を、ちり紙を膨らませた中に捕まえるとぼんぼりのようになります。暗いあぜ道を照らすぼんぼりを見つめながら家に戻ると二階の板の間に敷いた布団に横になります。ぼんぼりはどうしたのだろう。お母さんが中の蛍をどこかで逃がしてやったのだろうか。そんなことを考えながら眠りにつくのでした。
その真夜中のことでした。光がど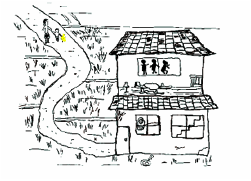 こにも差さない部屋は真っ暗でした。それにもかかわらず、雨戸の部分に三人の人物らしき影が大きく映り、回り灯籠のようにくるくると回るのです。お母さんあれは?と母を呼び起こし、母は電気スタンドをつけます。そうすると影は消えてしまうのです。もう寝なさい、そういって母が電気を消すと、一時してまた三人の影が現れるのでした。
こにも差さない部屋は真っ暗でした。それにもかかわらず、雨戸の部分に三人の人物らしき影が大きく映り、回り灯籠のようにくるくると回るのです。お母さんあれは?と母を呼び起こし、母は電気スタンドをつけます。そうすると影は消えてしまうのです。もう寝なさい、そういって母が電気を消すと、一時してまた三人の影が現れるのでした。
これが数回繰り返されました。電気を消すたびに三人の影が現れ出ます。他愛のないそれだけの話です。しかし事実としてはっきりと覚えています。そしてこの経験は今もって私にとってのほのかな希望に結びついています。それは私たち人類が世間という社会の中では、孤立して錯綜しあっていますが、心の奥底では精神や精霊のような目に見えぬ絆によってどこかで結びついているのではないかという思いです。そしてこの思いは未来に向かう人類という作品の創造にほんの少しでも自分も関わっているのかもしれないという思いにつながります。
ドイツの哲学者カントが「実践理性批判」で述べた大いなる神秘、「わが外なる大いなる宇宙と我が内なる大いなる道徳律」、この神秘が単なる理論的な帰結であるだけなら、わたしたちは大いなる輪廻と人間社会の混沌とむなしさを前にしてただただ呆然とするだけでしょう。
(注9)
そうではなく、私たちはおそらく神秘としか言いようがない事実にいつかは出会う存在ではないでしょうか。財産や地位や名誉、愛の獲得や富裕な生活からはどんなにかけ離れていても、なお、未来に向かって生きていけるのはそのような神秘や精神との出会いがあるからこそではないでしょうか。人間は神秘をも生きる存在だと思います。
そんなことも思い出されて、わたしはまだわずかに輝く山並みの稜線を眺め続けます。
7 犬車を押す女
もうひとつ、忘れがたい少年時代の思い出があります。小学五,六年生のころだったと思います。その当時は父の仕事の都合で自宅は街中の狭い長屋に移っていました。昼下がりに近くの道路を歩いていたら犬車を押す女に出会ったのです。犬車なんていう言い方があればですが、まさしく荷車のようなものを犬が引っ張っているのです。当時はまだ時折大きな荷車を馬が引っ張っていくのを見かけました。しかし犬が引っ張っているのを見たのは、これが最初で最後でした。青白い形相をして、女が犬車の側面を押しながら、時折棒のようなもので犬をたたくのでした。犬までも青白い形相で息も絶え絶えに前へ進もうとするのですが、青白い形相をした女は首に巻いた手ぬぐいで顔の汗をぬぐいながら、犬を怒鳴りつけ、何か重い荷物の載った犬車を前へ前へと進めようとしているのです。犬は大柄なシェパードほどの大きさでしたが、とても前へ進めそうな荷物の量ではありません。それでも女は悲痛な叫びを上げながら犬をたたきます。犬はただ そのような異様な光景を眺めながら、そのままその場を立ち去ったのを覚えています。問題はそれからでした。なすすべもなくそのまま立ち去ったことが重く心にのしかかってきたのです。おばさん、犬がかわいそうですよ!死んでしまいますよ!僕も手伝いますから犬をたたくのはやめてください。どうしてそうしたことがいえなかったのか、どうしてただただ見ているだけで、思い切って声がかけられなかったのか。それはもう重大な罪を背負ったかのように私を苦しめました。犬への憐憫だけではなく、犬の力までも絞りつくさなければならなかった女の不憫さにも苦しみました。思い出したくはないが、思い出さざるを得ない、逃げることのできない苦しみでした。 タラの芽庵では、たまにMDヘッドホンで音楽を聴きながら作業をすることもあります。最近よく聴くのは、小学校時代、菩提樹、野ばら、鱒などの歌曲で親しんだシューベルトの曲です。 「誰もが信念を持ってこの世に対する。それは理性や知識にはるかに優る。というのも、何事かを理解するにはまず信じなければならないからだ。」(注11) これらはシューベルトの言葉です。病に冒されながら31歳の若さでなくなった音楽家の言葉です。若くしてこのようなことを語る音楽家の生涯というものを考えてしまいます。彼の生涯は歌曲に明け暮れた生涯でした。彼は多くの人々に愛された、陽気な男でした。友人宅のどこにでも転がり込み、そこで曲を作り、友人たちと団欒しました。同時に彼は底知れない孤独や不治の病に侵されて苦しみ続けました。そうした彼の喜びと悲しみの生活が歌曲という芸術に凝縮されています。 ただあえぎながら少しずつ前へ進もうとするのです。
ただあえぎながら少しずつ前へ進もうとするのです。
そのような苦しみが数年続いたでしょうか。その後落ち着いた段階で考えたことは、人間の幸不幸というものは、死ぬまでにバランスの取れたものなのだろうか、それとも幸福に一生を終える人、不幸の連続で終える人、いろいろなのだろうか、ということでした。あの犬に荷物を引っ張らせざるを得ない不幸な女、あの後もとても幸せに巡り会いそうもないという気がする。
当時私と同じクラスの生徒はある石油会社の社長の息子で、ぐるっと高い石垣に囲まれた大きな邸宅に住んでいました。なぜか私には声がかかりませんでしたが、クラスの大勢が彼の誕生日に招待されて、すごいうち、すごいごちそうだったと言っていたのを覚えています。こうして本当に有り余る幸せに生きている連中もいる。でも本当にいつまでも幸せなのだろうか。あるいは本当にその同級生は自分が幸福だと感じていたのだろうか。不幸があるから幸福もあるのだろうか。あるいは幸福があるから不幸もあるのだろうか。だがあの犬をたたく女も、犬も、本当に不幸だった!なんということだろう。幸不幸の配分が本当に個々人にとって不平等であると考えざるを得ないとしたら、この社会に生きていくことは本当につらいことだ。大人たちはどう考えているのだろう。そんなことを真剣に考えたのを思い出します。
それからも考え続けました。多くの苦しみに遭遇し、耐えるということ、これは何を意味するのだろう。国連によればアフリカ、アジア、南アメリカなど、世界の5人に一人、10億人以上が一日一ドル以下で生活している、そして毎日5歳以下の子供35000人が飢えや防ぐことの出来る伝染病などで死んでいるといいます。多くの難民たちの苦難が続いています。多くの戦火や自然災害に多くの人々が苦しんでいます。暖かく休息したい。痛みから解放されたい。十分な食事が取りたい。失われたものを取り戻したい。加害者を糾弾したい。愛を獲得したい。平和な家族を持ちたい。楽しくみんなと遊びたい。一人でゆっくり音楽を聴きたい。知らないことを一杯勉強したい。自己の正当な要求を実現したい。これらが普通の人々の願いではないか。
世の中にはこれらの願望を実現できる人々と実現できない人々がいる。犯罪や事故、自然災害などの突然の不幸に襲われた人々、あるいは生まれながらの身体的境遇から不幸な生活を送らざるを得ない人々がいる。また、この世で幸福を実現できなくとも、貧しい生活の中からやっとためた資金を使い果たして厳しい巡礼に出かける人々もいる。死後の幸せを祈るというが。生前苦難に耐えれば死後は極楽というこの信仰の由来はなんなのだろう。この世界的に普遍の考え、現象は何を物語っているのだろう。そんなことを考えたこともありました。

私が南インドで会うことのできたアーチャリアの先代はガンジーとも会談した人ですが、彼のもとに西洋の婦人が訪れたときの話があります。西洋の婦人はマハーチャリア(偉大なアーチャリア)に問いただします。輪廻転生、前世から引き継がれた人間の再生の根拠はどこにあるのか、と。
彼は答えます。今すぐ近くの病院にいって、生まれたばかりの乳児を見てきなさいと。さっそく病院にいって赤ん坊たちをみてきた婦人は報告します。愛らしい子、不格好な子、まるまる太った子、骨と皮ばかりの子、金持ちの家庭に生まれたような子、貧しい家庭に生まれたような子等、様々であったと。
マハーチャリアは答えます。我々の現在の生命は我々が前世で行った善と悪によって決定されているという教義を受け入れないとしたら、どうして我々はこうした多様性や差異を認めることが許されるのだろうと。
人間は生まれながらにそれぞれである。生まれながらの資質、生まれながらの任務を持っている。道徳的な人間もいる。犯罪者たちもいる。善と悪が絡み合って様々な人間がいる。我の強いものもいる。ある程度我を抑えて耐えることの出来る人間もいる。こうした様々な人々が共存しそれなりに生きていく社会が人間社会なのだと。我々の誕生の原因は何か。我々が犯した罪や悪が誕生の原因である。同時に我々の血と肉が我々を苦しみに陥れる。こうして彼はヴェーダに基づき、人類という作品の悠久の連鎖として人々の幸不幸を説くのでした。8 シューベルトを聴こう
「苦悩は理性を磨き、心を強くする。それに対し、喜びは理性を無視しやすく、心を甘やかすか軽薄にする。自分のやっていることが最善で、それ以外のすべては無だということを、惨めな思いをしているたくさんの人たちに思い込ませようとする偏狭さを僕は心のそこから憎む。」(注10)
ところで前に述べたように、折口信夫の「死者の書」は奈良と大阪の県境にある二上山に沈む落陽が大いなる舞台設定になっていました。20年前、わたしが二上山に上ったとき、ふもとの山道にある寺院の門からはみ出した黒板に目が留まりました。そこには歌が書かれていました。
「人と生まれし悲しみに、人と生まれし喜びを知る」と。
悲しみのさなかに獲得した智慧こそ人間の喜びであるということなのでしょうか。しかし一方で、悲しみを通じてしか本当の喜びを知ることができない人間の生とは何なのだろうとそのとき思いました。あの犬車を押す女を見た後と同じような思いがよみがえってきたのです。また、この歌はいわれぬ罪を背に負わされて、若くして自害させられ、二上山に葬られた大津皇子の運命をも歌ったのだろうかとも思いました。一部の人々は、こうした英雄的人格の犠牲の上にその生きていく意味を見出してきたのかもしれないと思いました。私たち人類一般にも通じる思いなのだと。
シューベルトは英雄ではなかったにしても、あまりにも短い生を生き抜いた天才でした。そのことだけでも大いなる犠牲的精神を感じます。連祷というヤコービの詩につけたシューベルトの曲を聴いてみてください。連祷とは、司祭と信者が死者のために交互に唱える祈りのことだそうです。
「すべてこの世を去った者らの、すべての魂よ、安らかに憩え」と歌います。(注12)
「安らかに憩え、すべての魂よ。恐ろしい苦しみを味わった者も、甘美な夢にひたれた者も、生に満ちたりた者も、生を受けるや否や この世を去っていった者も、すべての魂よ、安らかに憩え!」(注13)
この世を去っていった者も、すべての魂よ、安らかに憩え!」(注13)
なんというおおらかな歌でしょう。このようなおおらかさは、生きることの喜び、憧れ、期待と同時にそのような感情の吐露を支えている、深い無の緊張、喜びとは裏腹の生のむなしさというようなものをそれなりに知っている人間にしか表現することは出来ません。そうした無の極地を見据えながら、祈るように芸術の創造に生きたのがシューベルトなのです。
「楽に寄す」という作品で歌っています。「美しき芸術よ、この世の世間的なおぞましさの中で、意気消沈した私の心を暖かい愛に燃えあがらせ、よりよき世界へと誘ってくれた芸術よ!」(注14)と。シューベルトにとって、祈りは我々が創造すべきものへの祈り、我々の芸術の可能性への祈り、それが生きていることだと信じる祈りでした。
さあ、あなたが意気消沈して生の意味が見いだせないとき,懸命に人を愛しても報われない時、能力以上の地位や名誉、あるいは財産のみを追い求めるこの世間というものに嫌気がさした時、さあ、どうか静かにシューベルトを聴いてみてください。歌曲のみならず管弦楽曲、室内楽やミサ曲などにもすばらしい名曲が見いだせます。芸術の創造への祈りが私たちに送り届けた人類の遺産です。
9 子供たちへ
こうして私の人生は家族と職場とタラの芽庵での出来事を中心に歳を経てきました。そして今やタラの芽庵の建設がスタートした当時、50代だった佐藤さんの年齢をとうにすぎてしまいました。小学生だった子供たちもここでタラの芽庵の建設を手伝ったり、牛と遊んだり、あるいは正月には餅つきをしたりして大きくなったのです。その子供達ももはや成人してみんなどこかで働いています。
【われわれ大人たちと一緒に】
世の中は少子化で人口が減ってきた、高齢化が進むと騒いでいます。育児ができる職場環境を整えなければということで、それはそれで大切なことです。しかし、大人たちがたくさん子供を生みたくないとしたら、それは生みたくないからとしか言いようがありません。お互い貧しくとも、おい、坊主、といって他人の子供の頭をくりくりとなでてあげるような、そんなおおらかな地域社会がなくなったといえば、それも少子化のひとつの理由かもしれません。坊主、頑張れよ、とどんな子供でも励ます世間の雰囲気がかすんできたといわれればそうかもしれません。なんだか今の世の中は頭の回転のよさや効率性だけがますます追求されていくようです。危害を加えるわけではなく、目立って役に立つわけでもなく、すみでぼんやりしている、でくの坊の子供には少し窮屈な世の中になってきたのかもしれません。
とはいえ先に世間について考えたように、世の中とは幾分そんなものだし、頭のいい連中やうまく立ち回る人間が名誉や財産や権力を独り占めにするのも世間というものです。だがそんなことは誰に教わらなくとも子供たちは体で覚えていくものです。子供たちは賢いものは賢いなりに、そうでないものはそうでないものなりに自分の居場所を自分で見つけていきます。大人たちが病んでいるに過ぎないのかもしれません。大人たちが子供を生み育てていく自信をなくしてきているに過ぎないのかもしれません。
だから子供たちの皆さん、大人たちを当てにするのではなく、人生は自分の本当にやりたいことを発見する大いなる旅路だと考えてみましょう。何をやらなければならないということはありません。何かを書物で学ぼうと思っても、大人たちの書物は大方がつまらんものです。あなたたちも大人になればその大方を作ったり読んだりするのかもしれません。でも本当に自分の欲するところや目指すところがしっくりすれば、そこからまた人間社会の新たな広がりが生まれてくるということです。倦まずあせらず、苦しみは苦しみとして、楽しみは楽しみとして受け入れながら、われわれ大人たちと一緒に生きていきましょう。
【豊かな 、たぐいまれなる現象の前に】
、たぐいまれなる現象の前に】
私の話も大人たちの大方のつまらない本と同じかもしれませんが、我々大人たちと一緒に生きてくれるのなら、どうかもう少し聞いてください。それは、未来に向かって私たちはどのような社会を目指していけばよいのかということについてです。そこで私は再びインドの世界に戻って、私のインド旅行で学んだことをあなた方に伝えたいと思うのです。それはヴェーダの教えとガンジーに学んだことでした。
ガンジーが学んだヴェーダの教えは言っています。人間は一人ひとり生まれながらの任務を背負ってこの世に生まれ落とされ
てきている。前世から引きつがれてきたものをも背負っていると。私自身の内部にもおそらく前世から引きつがれた怨念や傲慢さや弱さが宿っていることでしょう。そういう様々な善悪の因果を背負いながらこの世でそれぞれの社会的な任務を生きていくことが人間社会だというのです。
こうした教えを受けてガンジーは言います。「あなたの真実は自分自身の共感の深い井戸から生まれるべきものだ。故に真実を語るときは辛らつな言葉を避け、真実を語りながらも柔軟でなければならない。他者を思いやることは自分自身を思いやることでもある。他者に暴力を振る舞う時、自分自身にも暴力を振る舞っている。他者を中傷し辱める時、自分自身をも中傷し辱めているのである。怒りはそれを受ける人を動揺させる以上に、怒っている本人をかき乱す。」(注15)それぞれ悠久の過去から与えられたそれぞれの資質に従って、他人を思いやりながら生きていきなさい、と。
ではなぜ、非暴力、他者への思いやりが必要なのか。彼は言っています。「人間は他の形態の生命を奪ったり管理したり支配したりする絶対的権利など持っていない。そればかりか、人間は非暴力を実践し、生命世界の、謎に満ちた、偉大で豊かな、たぐいまれなる現象の前に謙虚であるという特別な任務を負っている」(注16)と。生命世界の、謎に満ちた、偉大で、豊かな、たぐいまれなる現象の前に謙虚であるという気持ち、この言葉が重要です。これが人類の英知を生んだヴェーダの世界なのです。ガンジーはそれをよく理解していました。この謎に満ちたたぐいまれなる多様な人間世界が暴力を許さないのです。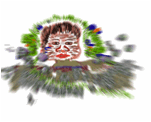
どういうことなのか。私はインドで多くの人々と出会いました。多くの表情と出会いました。端的に言えば、この表情が暴力を許さないのです。私は10数年前ある夢を見たことがありました。どこか刑務所のような所から脱走するために男が塀を乗り越えようとしているのです。男は私のほうを振り向きました。大きな茶褐色の、しわのよった顔でした。私はその男の表情になんとも言えず圧倒されたのでした。犯罪者かもしれないということはさらさら関係ありません。何かは分からないがただただすべてが凝縮されているその表情に感動したのです。それは本当にすべての苦難とすべての喜びを包摂するような、なんともいえない表情でした。畏敬さえ感じる表情、多様さを許容し、決して抹殺することはできない、抹殺しては我々人類そのものがだめになるとさえ思えるほどの表情でした。
インドでも同じような表情に何度か出会いました。私の出あった目の前のこの男は何者なのか。インドはそれを問う場所なのです。平和と民主主義の自由主義社会で、その他大勢として、一くくりにされる大衆としての一人ではなく、まさしくかけがえのない、彼自身でしかない一人に出会うのがインドなのです。そこが、ガンジーが生まれ、戦った場所なのです。では場所とは、人間が本来住むべき場所とは何なのか。
【適正規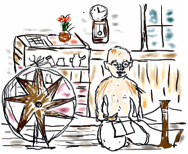 模の人間関係と相互扶助】
模の人間関係と相互扶助】
私たちがガンジーの写真でよく見るのは、彼が裸で手紡ぎ車を引いている姿です。ガンジーは言っています。手仕事は非暴力の文化であり、真に平和の経済である。手仕事はエコロジーと持続可能性を体現している。インドの村々の手仕事の伝統は未来の生活の最も適切な形である。もし村々が滅びるなら、インドも滅びるだろうと。
もし村々が滅びるなら、インドも滅びるという言葉が重要です。皆さんもご存知のように、今グローバル化した市場経済の世の中では、世界中で地域経済が、村々の生活が滅びてきています。ガンジーはそのことに警告を発しています。村々には百姓、鍛冶屋、大工、靴屋、小物売り、さらには人々がじかにその英知を認める祭司や神官、教師などが住んでいました。このようにその地域全体が人間社会として聖なる中心を持ち、ある程度の完結と一貫性を保持しているような世界、それが村だといいます。これに対して都市に集中する西洋の合理的、人道的な世界は生命なき機械を崇拝し、人々を朝早くから夜遅くまで果てしない労働と画一化された思考へと追いやってきました。ガンジーは西洋の合理主義、人道主義自体が精神的な暴力を宿しているのだとまで言っています。(注17)
市場経済のグローバル化はその世界中に張り巡らされた交通網と情報網によって自立した地域経済を破壊し、一部の人々はますます貪欲と浪費に専念すると同時に多くの人々が絶望的な貧困に追いやられてしまう。そこには本来人間にとってあるべき適正規模の人間関係と相互扶助は失われ、多くの人々の生活行動は市場経済の貨幣価値に還元されてしまうのです。(注18)
そして悲惨なことに、グローバル化し技術の発達で情報化が緻密になればなるほど、私たちは逆に、私たちから乖離し、私たちには統制することができない巨大な波に飲み込まれてしまうことになるのです。今回の世界同時金融危機はまさにそのようなことの顕著な現われでした。ガンジーはこのような現在の我々にとっても大きな課題を既に当時から見据えていたようにも思えます。
すべての人の必要を満たすにたるものが世界には存在するが、誰ものどん欲を満たすにたるものは存在しない、とガンジーは言っています。資本主義の先進諸国の生活を世界中の人が享受しようとすると、地球は4個も5個もあっても足りないと言うのです。どん欲と浪費が今地球の危機を招いています。人々は世界中にかってあった村々の豊かな貧しさというものを忘れて。
【外へ出て学ぼう】
「しかしどうなのだろう。」とどこかから声がします。「果てしない欲望の充足を求めて破滅へと向かうのも人類という作品のなすところではないのか。お前は、ヴェーダの教えでは、この世は善と悪のめくるめく展開する場所なのだ、この世であるかぎり悪が絶えないと言っているではないか。無用な果てしない争いは世の常であり、我々はまた途方もない過去の愚かな行為に縛られていると言っているではないか。」と。
その通りです。過去の愚かさから容易に脱却出来ると考えることも、あるいはグローバル化されていない古き良き時代の村に簡単に戻ることが出来ると考えることも現実の状況とはあまりにも乖離した考えです。
私たちが自ら制御し評価できる規模の地域経済とコミュニティーを取り戻すことは、未来へ向けての私たちの大きな課題です。しかしながら、そのような自ら制御し評価出来る地域社会はこれから本当に可能なのかという問いももちろん存在します。近代文明の技術的な成果を放棄して、大いなる過去へ戻れというのではありません。大切なのは過去から蓄積された人類の英知を我々はどのような形で受け継ぎ、それを未来へと伝えていけるかということです。
安易な言葉の整理で問題が解決出来るわけではありません。表面的に取り繕った政治的な言動だけで人々を動かそうとすることも行き止まりになりそうな気がします。我々には、時間をかけてでも、やはり、心の奥底から、複数の人々が自ら立ち上がるような、真実の現状分析と、真実の共通の願いが必要です。本当に出口がふさがっている人々に勇気を与えるような現状分析と共通の願いが。たとえば寓話のような形で。このような理想の集団、村々があった。それがこのようにして滅びた。そのような寓話が私たちの心を動かすのなら、それだけでも意味があるのです。
ですから理想的な人間社会がすぐにでも、一部にでも実現したように見えれば、それはまやかしかもしれません。まやかしではないものは当時の為政者たちから二上山に葬られた「死者の書」の大津皇子のように犠牲的精神でもって一度は滅ばなければならないのかもしれません。このことをしっかり覚えておいてください。このような犠牲的精神と連なって本当は、私たち一人ひとりは、個体以上のものなのです。個体以上のもの として未来に向かって進んでいるのです。
として未来に向かって進んでいるのです。
ですから子供たちのみなさん、日本の外へ一度は出て、未来に向かう仲間たちの生活を見てみましょう。日本人は今、都会でも村々でも出口のない閉塞感にとまどっています。数千年の文化の蓄積のある外へ出て海外の仲間たちから多くを学びましょう。そしてまた日本に帰ってきてまた違った目で我々日本人の良さを、課題を、考えてみてください。さらには海外の友人たちへの恩返しを、そして地球全体の未来を考えてみてください。
もちろん世界とてグローバル化の波にあって、ほとんどの地域は国家やマスコミに支配されています。しかしまだ南インドの村々のように、古来からの遺産を大切に受け継いでいる地域も残っています。そこには個人的な利益を追求する、忙しい時間や空間はなく、村としてのまとまりと、そこに住んでいるみんなの未来を真剣に考えている人々が住んでいます。
【国家間の争いの向こうに】
地球は生まれてから約46億年経過し、このあとの寿命は50億年足らずだといわれています。一方人類は約400万年前に猿から進化したといわれていますが、我々の先祖だといわれているホモサピエンスはまだ20万年前に生まれたばかりです。インダス川流域に古代文明が栄えたのは約4000年前、彼らの子孫が南インドに下ってヴェーダの教えを伝え始めたのは約3000年前頃からです。しかしながら産業革命後の私たちの機械文明が本格的に登場したのはわずか約200年前です。この200年間は私たち一人ひとりの寿命のおよそ三世代分に過ぎません。
この200年、私たちは人類の数千年に及ぶ知恵をどう生かしてきたのでしょうか。生かしきれずこれから千年も経過せずに消滅へと向かうのでしょうか。それとも地球が消滅するまで生き続けるのでしょうか。あと50億年です。なんとも桁外れの数字ですが。そしてその前に人類が地球に住めなくなったとしても、人類は技術の力で宇宙へと生活圏を広げていくのでしょうか。
宇宙空間では、人類にとって本来の生活規模とは何かが緊急の課題になって来ることでしょう。まさしく我々はこの地球に守られて生きているからこそ、急激に社会の規模を拡大し、過密化してきても、そのことを真剣に憂慮することはなかったのです。
しかし現在の地球はもはやそのような悠長な状況ではありません。この地球を救い、人類を救うためにも、子供たちの皆さん、どうか私たちと一緒にこれからの人間社会を考えていこうではありませんか。もう核を保有しあい、果てしない戦争で多くの犠牲を伴う国家間での馬鹿げた行為の繰り返しは終わりにしなければなりません。少し頭を冷やして、もっとましなことを一緒に考えていきましょう。(注19)
10 タラの芽庵の春
とうとう最後の章になりました。最近久しぶりに夢をみました。どこか遠くアジアのような場所に私は一人放浪の旅をしています。そして、あるにぎやかな市場のような場所にバスかなにかで到着するのです。ほこりっぽい道路の前方は少々上り坂。左側は、とてつもなく巨大な白い壁。この、天までも届くような途方もない壁の高さが印象的なのです。右側はベトナムやインドネシアのような市場の喧噪。さて自分はどうすれ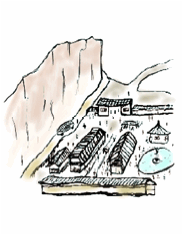 ばよいのか。だれかがにやにやと次の行動に移れない自分を見つめているような気がします。しかし機が熟してきたというか、荘厳な雰囲気があるのです。
ばよいのか。だれかがにやにやと次の行動に移れない自分を見つめているような気がします。しかし機が熟してきたというか、荘厳な雰囲気があるのです。
といっても現実の生活では、私には特別なことは何も出来ません。いつものように月に二三回はタラの芽庵を訪れて、ぼんやりして暮らします。特に春は山腹に霞が漂い、タラの周囲は梅に花大根、レンゲの花、やがてシイ、クス、タラなどの木々が芽吹き、初夏に向かうと甘い桑の実が熟してきます。
ぼんやりしながらもやらなければならない作業はいっぱいあります。入り口の重たいドアの蝶番がいかれてきました。ベランダが崩れかかっています。木食いありにやられた正面の丸太は早く手当をしないとタラの芽庵そのものが傾きそうです。
そんなこんなでつぎはぎだらけの作業でタラの芽庵もそして私も生きてきました。まさしく私自身の言葉もつぎはぎだらけで、本当にやるべきことを先へ延ばしながら生きてきたのかもしれません。私も60を過ぎてしまいました。あと何年生きられるでしょう。あと20年?それにしても人生はなんと短いことか。時はなんと無慈悲であることか。それでも残された時、与えられた時をしっかり生きよと何かが私をせきたてます。
夢で見たアジアは私が二年前に訪れたインドの町並みの喧騒にもつながっていきます。ひとつはコルカタでの出来事でした。地下鉄へ下る入り口で私をいぶかる警察官とむなしい問答を繰り返したあと、地下に降りて満員の電車に乗ったときのことでした。二三メートル先に座っていた若い男性が急に立ち上がって人ごみを掻き分けて私に席を譲ってくれたのです。男性は私から離れたところで終点までずっと立っていました。私が終点でお礼を言うと、はにかむようににこっと笑いながら立ち去っていきました。疲れ果ててさまよう異国の旅人を気の毒に思ったのでしょうか。
そしてもうひとつは、デリーで出会ったオートリクシャの運転手との出来事でした。インドの巷で出会った学生たちの多くは、ガンジーの非暴力や手仕事の伝統へのこだわりはナンセンスだと言います。そうした声に合わせるかのように、インドは経済的に急激に躍進しています。そんなデリーで、リクシャを運転しながら彼はあれがガンジーだと、道路際にあった記念像を示しました。そして私がガンジーイズグレイトと言うと、私を振り返って実に神妙にうなずいたのでした。あのコルカタの青年の笑顔と同じように、この年老いた運転手の味わい深い表情は、インドを放浪する私に贈られたささやかな啓示なんだと思いました。私は喧騒とスモッグの市内を巡りながらその思いだけでうれしくなりました。
私は帰国すると国語学者の大野先生に手紙を出しました。私が南インドでタミル人と間違われたこと、チェンナイ行政府の考古学者が、大野博士が20数年前、古代日本との文化比較のために、南インドのストーンサークルを見に来たことが記録に残っていると伝えてくれたことなどを。大野先生は非常に喜んで電話をくださいました。南インドは違う、インドの中でも南インドは特別だよと。そして様々な参考書も教えてくださいました。(注20)
まだお元気で頑張ってくださいと私がいうと、私はもうこの年だが、あなたはまだこれからだと、60歳になられてから南インドへ留学され、タミル語を一から学ばれた先生の言葉が返ってきました。しかしその先生も昨年88歳で亡くなられました。
与えられた残り少ない人生で何ができるのか。何かができるという慢心はありません。たいしたことはできません。しかし私にできることで、私だけでなくみんなが共有すべきことがあれば、それはささやかでも人々に伝えていきたいと思います。たいしたことはできないが、それしかできない。そんなところに一人間の残された人生は集約されていくような気もします。まさしく自由とはそんなものかもしれません。あれもこれも何でもできるということではなくこれしかできないという点に集約されていく人の生と言うもの。ヴェーダは教えます。
「大なる世界を得んと欲する者は常に知るべし、日は彼自身の相なり。
即ち全世界もまた彼自身の相なりと。一切の根、一切の体は老ゆ。意のみは老 ゆることなし。常に壮者のごとく迅速なり」(注21)と。
ゆることなし。常に壮者のごとく迅速なり」(注21)と。
そういうことです。春が来て夏が過ぎて秋になる、そして冬になると再び春を待つ。そんな繰り返しで私たちはいつか土に帰り、タラの芽庵もいつかは土に帰り、土からまたタラの芽が芽吹き、春が来て夏が過ぎて小鳥たちが木々を行き交い、ここ、私たちが生きてきた場所に再び生命がよみがえってくるのです。
(2009年3月25日 記)
脚注
(1)1943年現行版刊行、折口信夫全集24巻所収(中央公論社)。なお、折口信夫については、「タラの芽庵便り」のための
補足的な注解(以下「タラの芽庵注解」という。)の4を参照してください。
(2)仏陀の教えの背景にあるものを密教として深めた日本の思想家に空海がいます。空海についてはタラの芽庵注解の7を参照し
てください。
(3)私が訪れた教育施設は南インドのカーンチプラムにあります。その施設やアーチャリアについては、タラの芽庵注解の9を参
照してください。なお、通訳してくれたグル、アイヤーさん(S.Chidambaresa Iyer)とは現在もメールを交換しています。
彼はインド国鉄を退職した技術者のバラモンで、親切にも私にサンスクリットの手ほどきをしてくれています。
(4)ウパニシャッド全書八「アディヤートマ」Adbyatma神林隆浄訳(東方出版)。ヴェーダやウパニシャッドについては、
タラの芽庵注解の1を参照してください。
(5)ウパニシャッド全書一「ブリハッド・アーラニヤ」Brihad Araniyaka高楠順次郎訳(東方出版)
(9)カントについてはタラの芽庵注解の8を参照してください。
(10)シューベルトの手紙、実吉晴夫訳(メタモル出版)。シューベルトについてはタラの芽庵注解の11も参照してください。
(12)「F・ディースカウ、ザベストオブシューベルト」CD所収・西野茂雄訳 (東芝EMI,)
(15)ガンジー自伝、蝋山芳郎訳(中公文庫)。ガンジーについてはタラの芽庵注解の6も参照してください。
(17)ガンジーのカーストに対する考えについてはタラの芽庵注解5を参照してください。
(18)資本主義に関する諸問題についてはタラの芽庵注解の10を参照してください。
(19)机上の論理ではなく世界平和について考えた人としてザメンホフや宮沢賢治がいます。ザメンホフのエスペラントと世界
言語についてはタラの芽庵注解の2を、宮沢賢治についてはタラの芽庵注解の12を参照してください。
(20)この折り、先生にはちょうど発刊された最後の自著「日本語の源流を求めて」(岩波新書)も紹介していただきました。
先生の考えの経緯と要旨がよくまとめられています。なお、先生についてはタラの芽庵注解の3も参照してください。